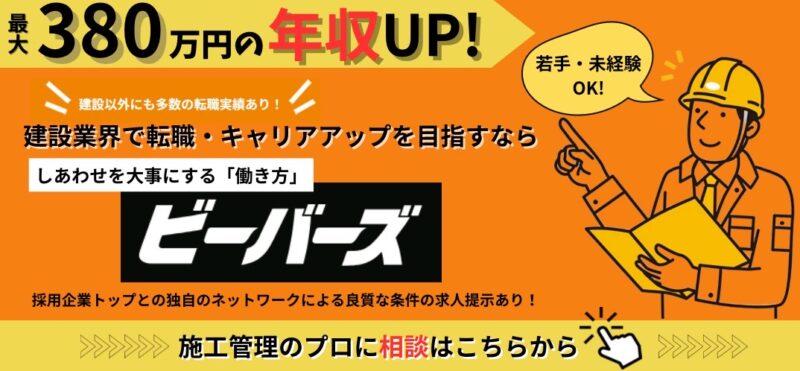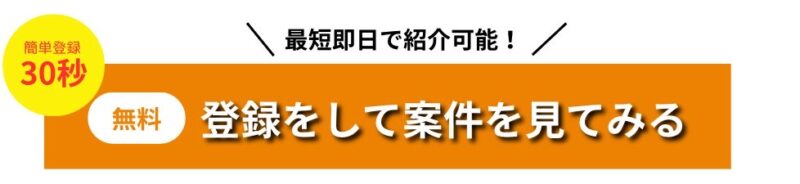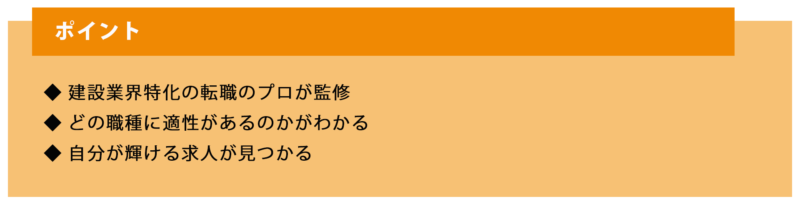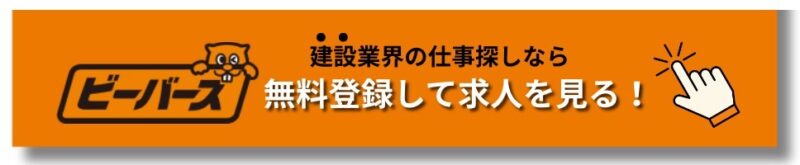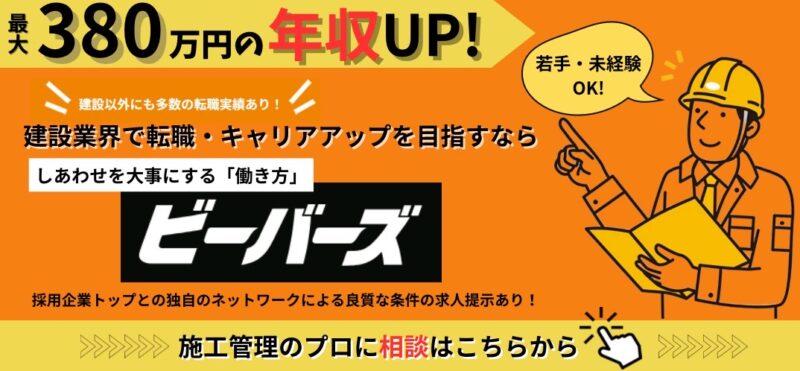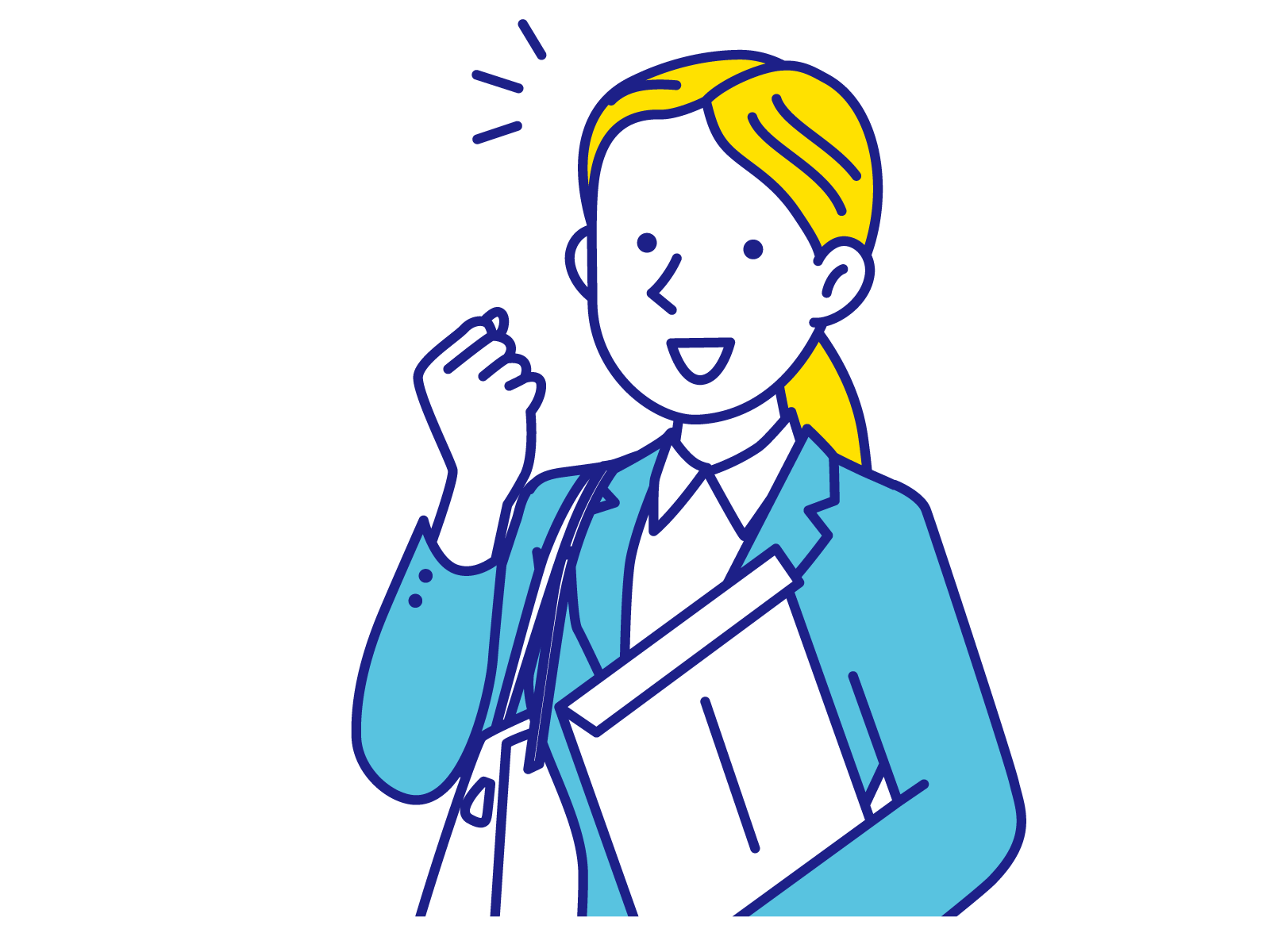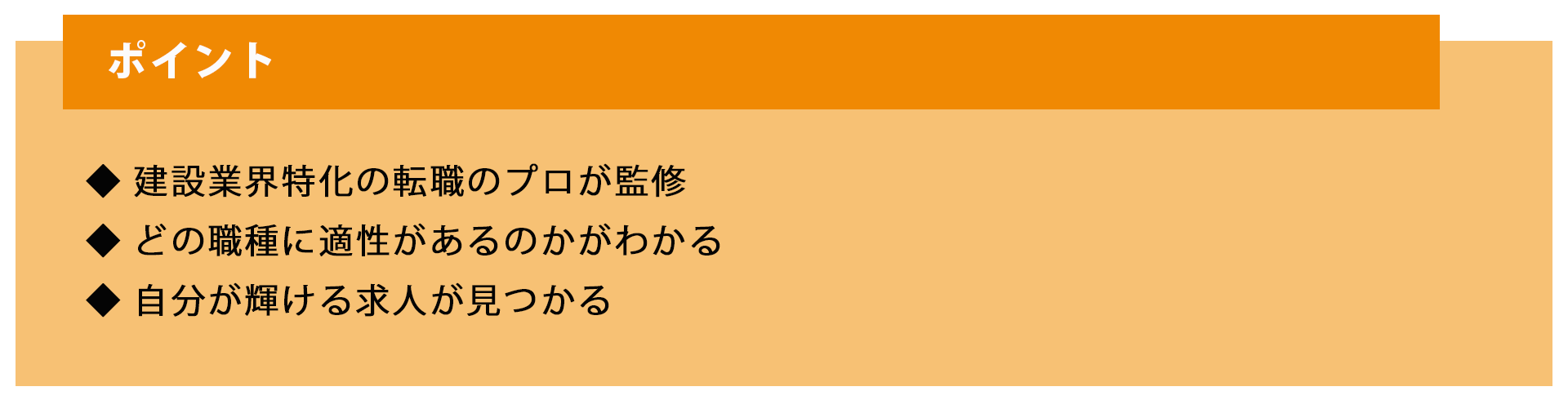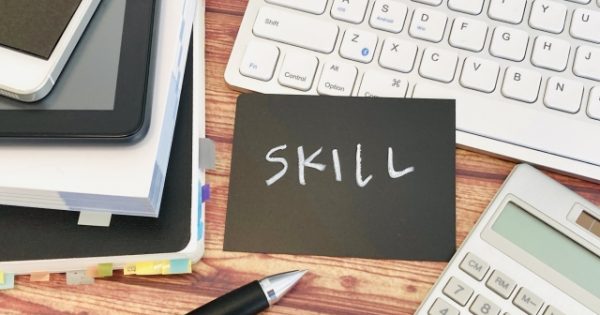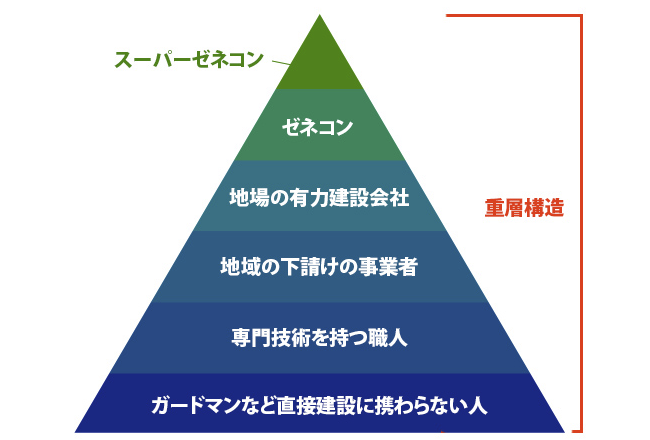施工管理と施工監理は似ているようで、それぞれ果たす役割や業務内容、必要な資格が異なります。
施工管理は工事の工程や安全、品質、原価など全体を実務的に統括し、現場の円滑な進行を担います。一方で施工監理は建築主の立場から設計図通りに工事が進んでいるかを確認する重要な業務です。
これらの違いを理解することで、現場で求められるスキルや資格の違いも明確になります。
そこで今回は、施工管理と施工監理の違いとは?業務内容や資格の違いを徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【未経験の方向け】転職活動の前に必ず適職診断をしよう
職種を変えるような転職活動では、 自分の適性を確認しておくことがとても大切です。
事前に適性を確認した上で進めることで、自分の想像とのギャップを確認することができます。
そこでビーバーズでは、無料で職種の向き不向きが診断できる適職診断ツールをご用意しました。
1分で簡単に、あなたの性格や特徴から職種への適性を診断できます!まだやっていない人は今すぐ診断しましょう!

施工管理と施工監理の基本的な違い

施工管理の役割と業務内容
施工管理は、建設現場において工事が予定通り、安全かつ効率的に進むように現場全体を統括・管理する業務です。主に、工程管理や品質管理、安全管理、原価管理、環境管理など多岐にわたる管理業務を行い、工事の実務的な進行を担います。
担当者は通常、施工業者側の現場監督(現場代理人)で、必要に応じて施工管理技士の資格を持つことがありますが、戸建住宅など小規模ケースでは資格なしでも可能な場合もあります。なお、資材の手配や労働力の確保、関係者の調整なども重要な役割です。
施工監理の役割と業務内容
施工監理は、建築主(発注者)の立場で、工事が設計図書や契約書に沿って適切に行われているかを確認・点検する業務です。設計者や建築士が担当し、工事品質の検査、問題点の指摘や是正指示を出すことが重要な役割です。
工事が設計通りに進んでいるか、指定資材が使われているか、手抜き工事がないかなどを厳しくチェックし、建築主に報告します。責任範囲が設計の適合性確認に特化しているため、資格(多くは建築士資格)の保有が必須です。
両者の目的と責任範囲の違い
施工管理と施工監理は、立場や目的が明確に異なります。
施工管理は施工業者側の立場で工事の円滑な進行を実務的・総合的に管理するのが目的です。対して施工監理は建築主側の立場で、工事が契約・設計図通りに適切に行われているかを監督・検証することが目的です。
この双方向の役割分担により、現場のミスやトラブルを未然に防ぎ、安全かつ高品質な建築物の完成に寄与します。
責任範囲も施工管理は工程・安全・原価など現場の広範なマネジメントに及び、施工監理は設計適合性と品質チェックに特化しています。
両者が互いに監視し合い、高い品質を保つ仕組みとなっているのです。
こちらも読まれています
【施工管理技士の副業】施工管理技士におすすめの副業とは?
弊社では、建設・不動産業界に携わる数多くの方の仕事探しを成功に導いております。転職、派遣、フリーランス、一人親方、建設業者全ての方々のニーズに適切な優良求人・案件をご紹介可能です。
- 完全週休2日制の求人
- 50代60代70代でも応募可能なお仕事
- 未経験でも応募可能なお仕事
- 高収入求人、高単価案件多数
- 無料登録から最短1週間で就業可能
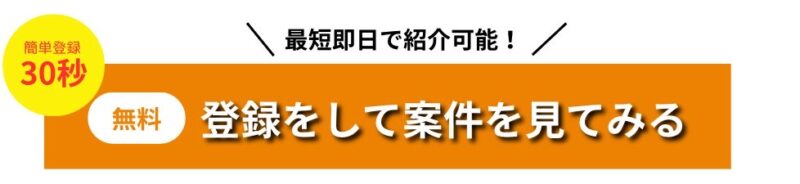
まずは無料登録をして色々な求人・案件を見てみてください。専門エージェントからおすすめの求人・案件をご紹介することも可能です。
施工管理の業務内容

工程管理とスケジュール調整
施工管理における工程管理は、工事の全体的な進行状況を把握し、計画通りに完成させるための調整を行う業務です。具体的には、工程表を作成して「誰がいつどこで何を行うか」を明確にし、資材や職人の手配、作業の順番や期間を管理します。天候などのリスクも考慮して予備日を設けるなどの柔軟な対応が求められます。問題や遅延が生じた場合は、工程表の見直しや関係者との調整によりスケジュールを再調整します。工程管理は工期を守るための根幹であり、無駄な時間やコストを削減する重要な役割を担います。
安全管理と労働環境の整備
安全管理では、作業員の安全を確保し労働災害を防止するため、現場の安全基準の遵守を徹底します。具体的には安全教育の実施、安全用品の準備、危険個所の確認と改善、作業環境の整備などを行います。労働環境の整備では、作業効率を高めるための作業スペースの確保や適切な休憩場所の設置、健康管理のサポートも含まれます。これにより事故や怪我のリスクを低減し、働きやすい環境を作ることが施工管理者の責任です。
品質管理と資材・機材の発注
品質管理は、設計図書や仕様書に基づき工事の品質を維持・向上させるための業務です。施工途中での検査や試験を行い、欠陥や不具合がないかを確認します。資材・機材の発注管理も重要で、適切なタイミングで必要な規格や数量の資材を用意し、納期遅れや過剰在庫を防ぎます。これには発注計画の立案、サプライヤーとの交渉、品質チェックも含まれます。品質とコストのバランスを保つことが求められます。
原価管理とコストコントロール
原価管理は、工事にかかる費用を計画通りに抑えるための管理で、資材費、人件費、機械使用料などのコストを詳細に把握・分析します。予算超過が見込まれる場合は原因を特定し、工事内容の調整や節約策を講じます。コストコントロールは利益確保のために不可欠であり、効率的な資源配分と無駄の排除が求められます。
関係者間の調整とコミュニケーション
施工管理では、発注者、設計者、施工業者、職人、資材業者など多くの関係者が関わるため、円滑なコミュニケーションと調整が欠かせません。工程変更やトラブル発生時には迅速に情報共有し、各担当者の役割や責任範囲を明確にして協力体制を構築します。定期的な会議や報告書作成、チャットツールや施工管理アプリの活用などが一般的です。適切な調整により現場の混乱を防ぎ、工事の質と安全を高めます.
施工管理の資格の種類や制度については、以下の記事をご参照ください。
関連記事:2級施工管理技士の難易度とは?令和6年度の試験制度改正や資格取得のメリットを解説
一方、監理技術者(主任技術者)は、建設業法で建築現場にいることが決められている存在であり、監理技術者は大規模な元請工事、主任技術者は小規模な元請工事、または下請け工事の現場において配置が必要とされています。
現場には常駐する必要があり、現場には最低一人いれば法律的には大丈夫ですが、有資格者の人数が多いほどその現場での仕事が信頼され、入札の際に有利になるといったメリットがあります。
給与面については、企業によっては資格保持者には数万円程度の資格手当が追加されることがあるため有利です。資格手当は企業により異なるため、資格を取得すると同時により良い待遇を求めて転職を考える人も多い傾向です。
施工管理と監理技術者の違いは、下記の記事も詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
関連記事:【管理(たけかん)と監理(さらかん)】工事管理と工事監理は違う?業務内容や、必要な資格の違いを徹底解説
こちらも読まれています
施工管理は未経験でもなれる!30代・40代でも転職に成功するコツや求人の探し方を解説【令和6年度改正版】
【施工管理志望の方向け】企業選びの前に必ず適職診断をしよう

転職・就職活動では、 自分の適性を確認しておくことがとても大切です。
事前に適性を確認した上で参加することで、自分の想像とのギャップを確認することができます。
そこでビーバーズでは、無料で業界の向き不向きが診断できる適職診断ツールをご用意しました。
1分で簡単に、あなたの性格や特徴から 職業への適性を診断できます!
診断は16タイプ診断に基づいています。 本格的求職活動が始まる前に適性を確認して、自信をもって求職活動を進めていきましょう!

施工監理の業務内容

設計図書との適合性の確認
施工監理は建築士法で「工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかを確認すること」と定められています。具体的には、設計図書をもとに作成された施工図や施工計画書が設計図書と相違ないかを厳しくチェックする仕事です。
この作業は、立会い確認(現場での目視や計測)、書類確認(提出された品質管理記録など)、抽出検査など合理的な方法で行われます。設計意図が正しく反映されているか、機能や性能が確保されているか、法規に適合しているかなど多面的に確認します。
施工図等の適正なチェックは、建物の完成品質に直結する重要な業務です。
工事の品質検査と問題点の是正指示
施工監理者は施工の各段階で実施される工事が設計図書通りに行われているかの品質検査を行います。
チェックの結果、問題点や設計図との相違が認められた場合は、施工業者に対して是正指示を出します。もし指示に従わない場合はその旨を建築主に報告し、品質確保のために必要な措置を求めなければなりません。
これにより設計図に基づく高品質な施工を促し、手抜き工事や不適合を防止する役割を担います。
建築主の代理としての報告責任
施工監理者は建築主の代理人として工事状況の報告義務を負います。
具体的には、設計図書との照合結果や品質検査の状況、問題や遅延の発生状況などを適宜建築主へ報告し、施工の透明性を確保するのが目的です。
また、法令違反や重大な不適合があった場合には速やかに伝え、建築主の利益を守る責任があります。
建築士や設計者との連携
施工監理は設計者(多くは建築士)と密接に連携しながら行います。
施工図の検討や施工計画の確認、工事中の設計改変の協議など継続的に情報交換を行い、設計意図が現場で正確に実現されるよう調整します。
現場での細かい状況変化に対応するため設計者の助言や承認を仰ぐことが不可欠です。
施工業者への指導とアドバイス
施工業者に対して設計図書通りの施工を促すため、指導や助言を行うのも施工管理者の重要な役割です。これには施工方法の改善提案や資材選定の確認、工事手順の指示などが含まれます。
適切な指導により、施工の品質を保つだけでなく、施工業者との良好な関係構築を通じてスムーズな工事進行を支えます。
こちらも読まれています
施工管理と施工監理に必要な資格の違い

施工管理技士(1級・2級)の概要と取得条件
1級建築施工管理技士は国土交通省管轄の国家資格で、試験は「第一次検定」と「第二次検定」に分かれます。令和6年度以降の改正により、第一次検定は受験年度末に満19歳以上であれば学歴に関わらず受験可能です。
第二次検定の受験には、第一次検定合格後の実務経験5年以上、または特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験などが必要です。2級建築施工管理技士の第二次検定合格者は、1級第一次検定の合格後に実務経験を経て1級を目指せます。
2級建築施工管理技士の第一次検定は17歳以上なら誰でも受験でき、第二次検定には一定の実務経験が求められます(令和6年度改正により要件が見直されています)。
施工管理技士の資格があると、特定建設業の許可に必要な監理技術者や主任技術者として認定されるため、現場責任者としての業務が遂行できます。
建築士資格が求められる施工監理の要件
施工監理は建築主や設計者の立場から工事が設計図書通りに進んでいるかを確認する役割であり、多くは建築士資格(1級建築士、2級建築士など)が必須とされます。
建築士は建築物の設計と監理(設計図との適合性の確認、品質検査、報告義務など)を法的に行う権限があり、建築士法に基づく業務を遂行します。
施工監理は工事の設計適合性を責任を持って監督し、設計図書とのズレや施工不良の是正指示を行うため、専門的な建築知識と資格が重要です[(前回答含む)]。
資格保有者の役割と責任範囲の違い
施工管理技士は施工業者側の現場責任者として、工程・安全・品質・原価管理の総合的な現場管理を担当。工事の円滑な進行や労働者の安全維持、工程調整など実務的管理責任があります。
建築士(施工監理者)は設計者または建築主の代理人として、設計図通りの施工を監督し、施工品質の適正や法令遵守を厳格にチェックする責任を負います。工事が設計基準から逸脱しないか、適切に報告・指導する役割が大きいです。
両者は立場も責任範囲も異なり、施工管理技士が実務的な現場管理を担い、建築士が設計適合性の監理役を務めることで相互のチェック・バランスを保っています。
資格取得によるキャリアの違いとメリット
1級建築施工管理技士の資格は建設業の現場監理技術者として高い評価を受け、特定建設業の監理技術者資格要件を満たし、現場責任者や管理職としてのキャリアアップに直結します。2級資格は主に中小規模の現場や補助的管理職に適します。
建築士資格は施工監理のみならず設計業務も担えるため、業務範囲が広く、建築設計事務所や施工監理事務所で重宝されます。設計者としてのキャリアパスや独立も可能です。
両者の資格取得は、それぞれの専門分野での信頼性向上、責任ある業務遂行、待遇改善や独立開業の基盤となるため、専門性と市場価値の向上に寄与します。
施工管理と施工監理の立場と関係性

工事現場における両者の役割分担
施工管理は施工業者側の立場で、工事の工程管理、安全管理、品質管理、原価管理など現場の実務全般を統括し、工事を安全・確実・効率的に進める役割です。具体的には、作業の段取り調整、資材や人員の手配、進捗管理、労働環境の整備などを行います。
一方、施工監理は発注者側(建築主や設計者の代理)として、工事が設計図書や契約内容に適合しているかを確認・チェックし、問題があれば是正指示を出し、工事品質の維持を担当します。
つまり、施工管理は「現場の実行と運営」を行い、施工監理は「設計通りの施工の確認と監督」を行うのが役割です。
発注者と施工者の視点の違い
施工監理は発注者の視点から、設計図通りに工事が行われているかを監視し、建築主の利益を守る役割です。設計の専門知識を活かし、施工の品質や適法性の確保と報告責任を負います。
対して施工管理は施工者側の視点で、工事を円滑かつ安全に進めるための現場運営と問題解決を行います。
両者はそれぞれ異なる利益と責任を持ちながらも、建設物の完成を目的とした相互補完的な関係にあるといえるでしょう。
トラブル防止と品質確保に向けた連携方法
トラブル防止には、両者間で役割や責任の明確化が不可欠です。具体的には、工事開始前のキックオフミーティングで「誰がいつどの段階で何を判断・報告するか」を共有し、施工監理者からの設計変更や是正指示に対して施工管理者が実務的に対応できる体制を整えます。
日々のコミュニケーションや定期的な進捗確認を密に行い、双方が情報を共有して協力することで、指示の食い違いや対応遅れを防ぎます。また、問題発生時の速やかな連絡・報告ルートを確立することも重要です。
両者が果たすべき社会的責任
施工管理者は現場の安全管理、労働者の健康保持、環境への配慮、工事の品質と工程の適正管理を担い、事故やトラブルの防止に責任を持ちます。
一方、施工監理者は建築物の安全性・耐久性を確保し、設計基準と法規制が守られていることを監督・確認し、発注者の権利保護や公共の安全確保に寄与します。
このように、両者はそれぞれ建設物の高品質・安全完成という社会的使命を共有し、適正な施工体制を維持するための重要な役割を果たしているのです。
施工管理・施工監理の現場での課題と今後の展望

人材不足の状況と育成の課題
建設業界全体で深刻な人手不足が続いており、施工管理や施工監理の現場も例外ではありません。特に若年層の入職減少やベテラン技術者の高齢化により、技術継承が進みにくい状況です。
現場では多忙かつ複雑な作業が求められ、長時間労働や現場外での書類作成など負担が大きく、離職率の増加や人材確保の困難さが問題となっています。育成面ではOJTによる技術伝承だけでなく、体系的な教育や資格取得支援、メンター制度などの整備が必要とされています。
DXやIT化による業務効率化の動向
建設業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速しており、施工管理や施工監理の業務効率化に寄与しています。具体的にはBIM(Building Information Modeling)の普及による施工計画の精度向上、AIを活用した進捗管理や品質検査、ドローンやIoTセンサーによる安全管理の自動化が進展しています。
また、電子契約や電子入札によるバックオフィス業務の効率化も進んでおり、現場技術者の負担軽減や多現場管理の実現にもつながっています。ICT活用は2024年に施行された法令改正にも後押しされており、今後一層普及が期待されるところです。
資格制度や業界の変化への対応策
2024年以降、建設業法の改正により、現場の監理技術者や主任技術者の専任義務の合理化などの制度変化がありました。これらはICT活用による現場管理効率化を促進し、多現場管理の可能性を広げています。
一方で、資格取得や技術力の維持・向上のための継続的な教育も重要視されています。業界は今後、変化する労働環境や環境対応義務(カーボンニュートラル対応など)に適応するため、新資格制度の整備や資格要件の見直しが進む可能性があります。
企業は法改正と連動した人材配置計画や研修制度の強化を進める必要があります。
今後のキャリアパスと展望
施工管理および施工監理の分野では、DXの活用や多現場兼務の進展により従来とは異なるキャリアパスが生まれつつあります。これまで現場に常駐していた技術者も、ICTを活用して複数現場を効率的に管理する役割が増えるでしょう。
資格保持者は技術専門職としての地位を強化でき、デジタル技術の専門家やプロジェクトマネージャーとしての道も広がっています。また、働き方改革により労働時間の短縮やワークライフバランスの改善が図られ、若い人材の定着が期待されます。
しかし一方で、高度なデジタルスキルの習得や継続教育が不可欠となり、職能転換支援や教育システムの充実が今後のポイントとなるでしょう。
これらの課題と展望を踏まえ、施工管理・施工監理の現場はデジタル化や人材育成の進化によって変革期を迎えており、企業・個人双方での戦略的対応が不可欠となっています。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
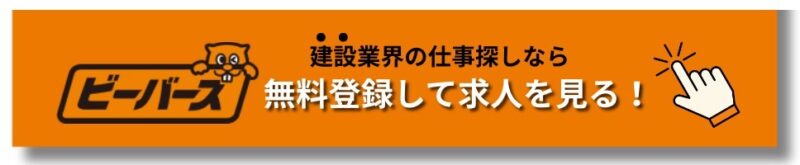
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
まとめ
施工管理と施工監理では立場や業務内容が大きく異なり、必要とされる資格も大きく違います。
建築業界に関わる上で、自分がどのようにキャリアアップをおこなっていきたいのか、その違いを理解した上で考えてみると良いでしょう。
転職エージェントのキャリアコンサルタントのサポートを受けながら就職や転職活動を進められれば、転職に関する悩みを解消できるだけでなく、自己分析やヒアリングを通して自分の向いている仕事に気付けるかもしれません。
特化型の転職エージェント「ビーバーズ」では、自己分析のサポートをしながら、あなたに合った転職先を提案いたします。
まずはお気軽に登録して、転職に関する悩みや疑問を相談してください。