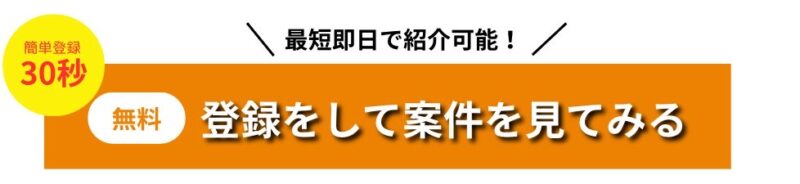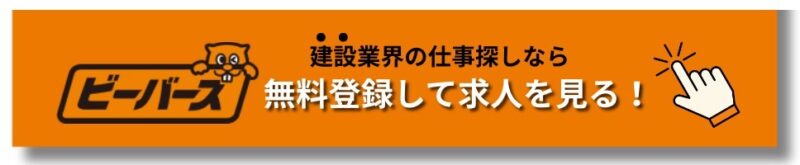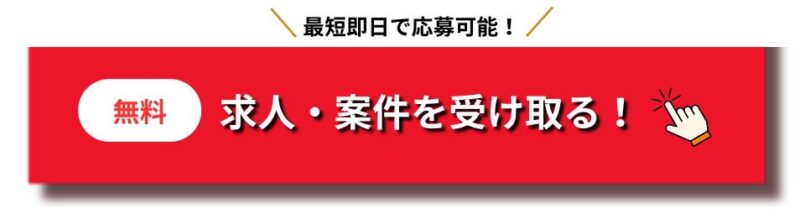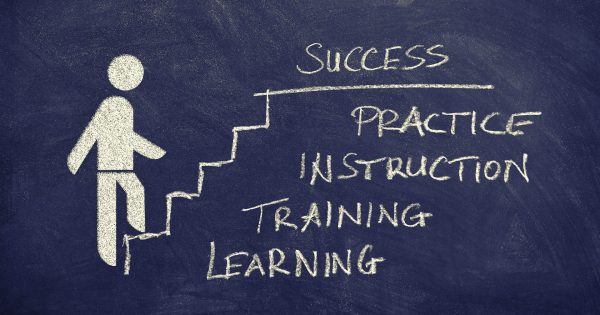マンション管理士とは、マンションの管理組合や区分所有者からの相談に応じて、助言や指導などを行う国家資格です。マンション管理士資格を取得するための国家試験に合格することは、不動産業界での専門性を高めるための重要なステップとなります。
ただし、マンション管理士の試験は難易度が高く、合格率は10%未満と難関です。しかし、適切な勉強方法と計画を立てれば、独学でも十分に合格は可能です。
そこで今回は、マンション管理士試験に独学で合格するための勉強時間の目安や、効果的な勉強方法を徹底解説します。これからマンション管理士を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
マンション管理士とは?仕事内容や資格の概要を解説

マンション管理士とは、マンションの適切な維持や管理に関する専門知識を持ち、管理組合のサポートやコンサルティングを行う国家資格者のことです。
マンション管理士は、2001年に施行された「マンション管理適正化法」によって設けられた比較的新しい資格で、マンション管理組合の運営をサポートし、適正なマンション管理を通じて良質なマンションストック(中古マンション)の形成に貢献します。
マンション管理士の仕事内容
マンション管理士の主な仕事内容には、以下のようなものがあります。
- 管理費や修繕積立金の会計監査
- 予算案や予算改定案の作成
- 総会や理事会の運営サポート
- 管理規約の改正や見直し
- 管理コストの見直しや削減
- マンション分譲に関する相談や助言
- 管理委託会社の選定や変更
- 災害時の緊急補修や大規模修繕の計画立案
- 住民間のトラブル解決
マンション管理士の資格を取得するメリット
資格取得のメリットとしては、不動産管理会社への就職・転職に有利であり、やりがいのある仕事であること、人脈を構築できること、資格手当の可能性があること、高齢者でも活躍可能なこと、将来性があること、独立開業の可能性があることなどが挙げられます。
マンション管理士の資格を取得する方法
マンション管理士になるためには、国家試験に合格する必要があります。ただし、マンション管理士の試験は、マンション管理に関する法令や実務、建物構造や設備に関する知識など、出題範囲が幅広いのが特徴です。
そのため試験の合格率は10%未満となっており、難易度の高い資格ですが、その専門性からマンション管理業界では重宝される資格と言えるでしょう。
資格取得に向けた学習方法や試験対策については、専門の転職エージェントからのアドバイスを受けるのも有効です。
マンション管理士試験は独学で合格できる?難易度や合格率を解説
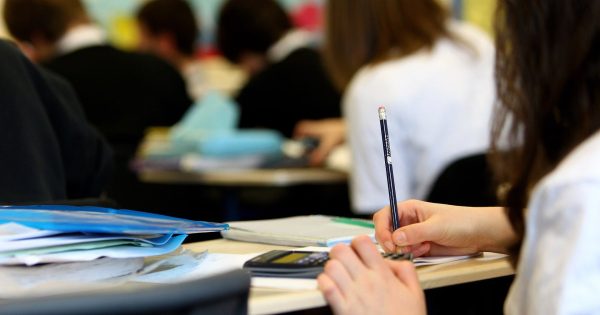
マンション管理士試験は、独学での合格も十分可能ですが、そのためには相応の努力と計画的な学習が必要です。試験の難易度は高く、合格率は例年7%から9%台とされています。
マンション管理士の難易度と合格率の詳細
過去数年の合格率は、8.2%から11.5%で推移しており、近年は10%を超えることもありますが、依然として難関試験の一つとされています。
合格点は、50問中35点から40点で、正答率は70%から80%が必要とされています。
独学での合格に向けた勉強時間
独学での合格には、最低でも500〜600時間以上の勉強が必要です。特に不動産関連の知識や経験がない初学者の場合には、700時間以上を見込むことが安全との意見もあります。
独学での学習方法
マンション管理士の資格に独学で挑戦する際には、次のポイントを押さえた学習法が重要です。
- 計画的な学習スケジュールを作成する
- 質の高い教材を選ぶ
- 模擬試験を活用する
- 弱点を克服する
マンション管理士試験を受験する際の注意点
管理業務主任者試験の合格者は、マンション管理士試験の一部が免除されるため、有利に受験できる制度があります。
また、独学が難しいと感じる場合は、通信講座や予備校の利用も検討すると良いでしょう。
しっかりとした準備と勉強を行えば、独学でもマンション管理士試験の合格は目指せますので、計画的に、そして着実に学習を進めていきましょう。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
マンション管理士試験の合格に必要な勉強時間の目安と効果的な勉強方法

マンション管理士試験の合格に必要な勉強時間の目安は、個人の学習状況や経験によって異なりますが、一般的には以下のようなガイドラインがあります。
マンション管理士試験の勉強時間の目安
マンション管理士を独学で合格するための勉強時間の目安は、先に少し触れましたが、初学者で約700時間の学習が推奨されています。これは、法令や実務、建物構造などの幅広い知識を身につけるためです。
一方、不動産業界や建築業界など関連する業務経験がある方の場合には、約500時間から600時間の学習が目安とされています。
マンション管理士試験の効率的な学習計画の立て方
マンション管理士に独学で合格するためには、まず学習スケジュールの作成が重要です。 毎日または毎週の学習時間を決め、長期的な計画を立てましょう。
次に、適切な教材を選定します。特に、最新の法改正に対応した教材を選び、理解を深めるために幅広い資料を活用することが重要です。
そして、定期的な復習と継続した学習が、独学で合格するためのポイントです。定期的に学習内容を復習し、知識の定着を図りましょう。
また、模擬試験の活用も有効です。実際の試験形式に慣れるために、模擬試験を定期的に行い、弱点を分析します。
マンション管理士試験の学習のポイント
マンション管理士の学習ポイントは、まず基礎知識の確認が大切です。マンション管理に関する基本的な知識から始め、徐々に専門的な内容へと進んでいきます。
次に、法令の理解です。マンション管理に関わる法令は頻繁に改正されるため、最新の情報を把握することが重要です。
また、実務経験を活用することで、より効率よく学習することができます。実際のマンション管理の現場での経験があれば、それを活かして具体的な事例を理解しましょう。
マンション管理士試験を独学するメリット
マンション管理士試験を独学するメリットは、まず自分のペースで学習できることです。 自分の生活リズムに合わせて学習を進めることができます。
また、資格を取得するまでにかかるコストを削減できるのもメリットです。予備校や通信講座に比べて、学習にかかる費用を抑えることができます。
マンション管理士試験を独学するデメリット
一方、マンション管理士試験を独学するデメリットとしては、自己管理の難しさが挙げられます。学習計画を自分自身で管理し続ける必要がありますが、これは非常に大変です。また、常に最新の情報を自分で集める努力が必要です。
独学での合格は、計画的な学習と自己管理がカギとなります。しっかりとした準備と努力を重ねれば、合格を目指すことができるでしょう。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
マンション管理士試験独学合格者が語る勉強のコツ

マンション管理士試験に独学で合格した方々が共有する勉強のコツは、以下のようなものがあります。
勉強スケジュールを作成すること
合格に必要な勉強時間の目安から逆算して、毎日の勉強スケジュールを作成しましょう。
例えば、600時間の勉強が必要なら、10ヶ月間で計画を立てると、1日約2時間の学習が必要になります。
勉強時間を確保すること
日々の忙しさの中でも勉強時間を作る努力が重要です。
朝早く起きる、通勤時間を利用する、夜の時間を確保するなど、自分のライフスタイルに合わせた時間の確保がポイントです。
質の高い教材を選定すること
最新版の良質なテキストや問題集を選び、インプットとアウトプットを繰り返し行います。同じテキストを何度も読み込み、過去問題を解いて理解を深めることが大切です。
反復練習の重要性を理解すること
学んだ知識を定着させるためには、インプットとアウトプットの反復継続が重要です。
理解を深めるためには、テキストの通読と過去問の学習・反復を重ねることが効果的です。
メリハリある勉強を継続して行うこと
分野によって出題数が異なるため、重点を置くべき分野を見極め、効率的かつ継続的に学習することが重要です。
出題傾向を分析し、得点しやすい分野から攻める戦略を立てましょう。
模擬試験を活用すること
実際の試験に慣れるために、模擬試験を利用して自己分析を行い、試験の場慣れをすることが有効です。
また、模擬試験の受験は、試験形式に慣れ、時間配分を学ぶことにも繋がります。
これらのコツを参考に、自分に合った勉強法を見つけ、計画的に学習を進めていくことが、独学での合格へのポイントとなるでしょう。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
マンション管理士試験に独学で合格するための勉強法のまとめ
このように、マンション管理士の仕事に就くためには、マンション管理士試験という難易度の高い国家試験に合格する必要があります。
マンション管理士試験の合格率は10%未満と非常に低いため、独学で合格するには、効率的かつ効果的な勉強法を取り入れ、計画的な学習を継続することが大切です。
ただし、資格を取得したからといって必ず成功するとは限りません。なぜなら、マンション管理士の仕事には、高いコミュニケーション能力や問題解決力といったスキルが必要だからです。
しかし、マンション管理士の適正のある方であれば、安定した仕事と収入に期待ができる人気の仕事に就くことができるでしょう。
そこでまずは、ご自身がマンション管理士の仕事が本当に合っているかをしっかりと自己分析しておくことが大切です。
そこで、不動産業界に特化した転職エージェントのサポートを受けながら転職活動を進めることで、仕事に関する悩みを解消できる可能性が高まります。
また、専属のキャリアコンサルタントが、あなたの適性や客観的に自己分析してくれるため、ご自分に本当に向いている職種に気付けるかもしれません。
特化型の転職エージェント「ランダーズ」では、自己分析のサポートをしながら、あなたに合った転職先を提案いたします。
まずはお気軽に登録して、転職に関する悩みや疑問を相談してください。