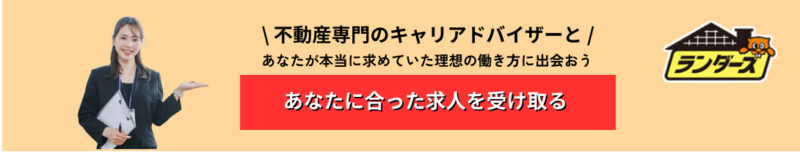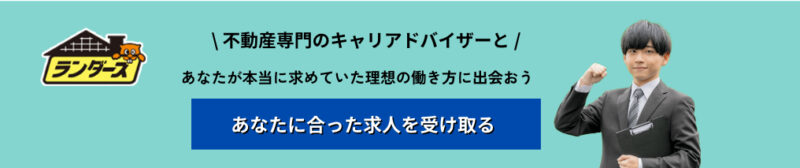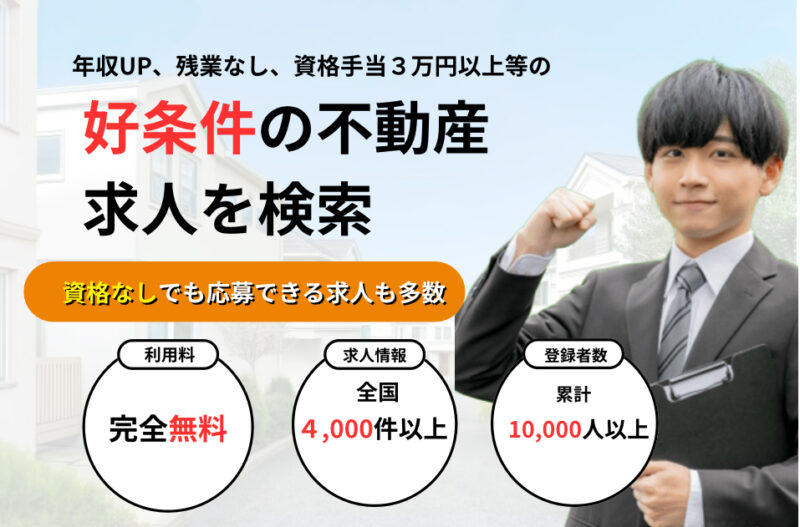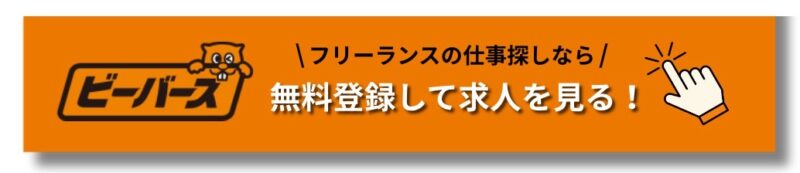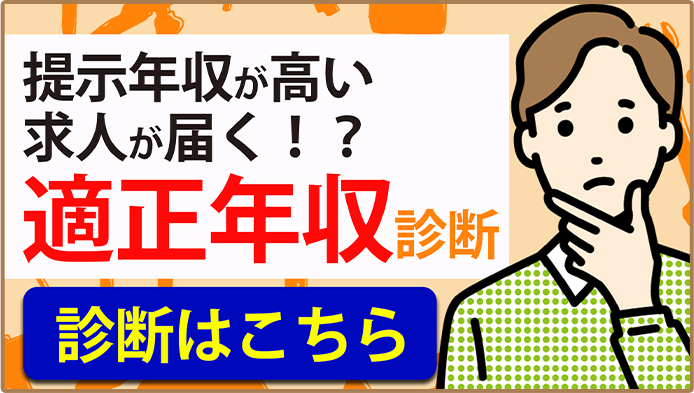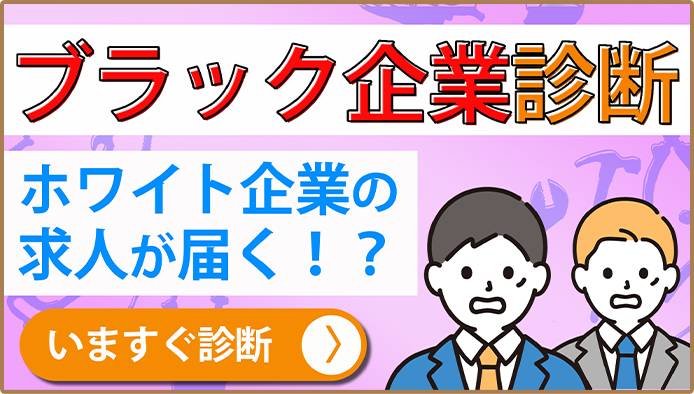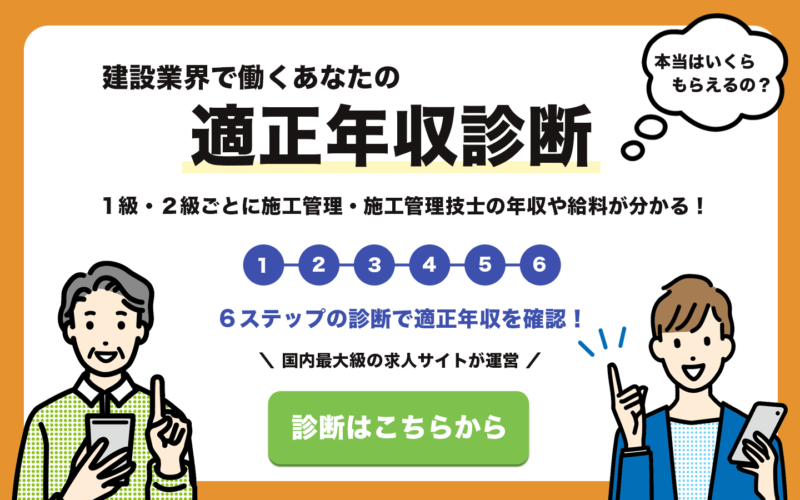土地家屋調査士はやめとけ・きついと言われる理由や将来性、年収などを徹底解説
不動産 土地家屋調査士 独立・フリーランス 働き方やキャリア 転職土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記や登記申請、審査請求、筆界特定、紛争解決などの手続きを行う専門家です。
土地家屋調査士は、不動産の物理的な状況を正確に把握し、登記簿に反映させるための調査や測量を行うのが主な仕事です。また、不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理することや、土地の筆界が明らかでないことを原因とする、民事的な紛争に係る民間紛争解決手続の代理も行います。
このように、土地家屋調査士の仕事は一見地味でありながら、不動産取引の安全を確保し、国民の財産を明確にするという公共性の高い仕事と言えるでしょう。また、その仕事内容から、土地家屋調査士は「やめとけ」や「きつい」などと言われることがあるようです。
しかし、土地家屋調査士の仕事には、大きなやりがいや将来性があるのも事実です。
そこで今回は、土地家屋調査士はやめとけやきついと言われる理由、将来性、年収などを徹底解説します。土地家屋調査士の仕事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
土地家屋調査士とは?仕事内容や資格の難易度を解説

土地家屋調査士とは、不動産の登記に関する専門家です。土地や建物の測量や調査を行い、法務局に登記の申請を代行することができます。また、土地の境界紛争の解決手段として、筆界特定を行うことも可能です。
これらの業務は、土地家屋調査士の資格保有者だけが行える独占業務です。
土地家屋調査士の主な仕事内容
土地家屋調査士の主な仕事内容は、不動産の現況を正確に調査・測量し、その結果をもとに「表示に関する登記」を行い、所有権など権利の明確化を支える専門業務です。以下で、具体的な業務内容を解説します。
不動産の調査・測量
土地や建物の正確な位置・形・面積を把握するため、現地調査や測量を実施します。古い地図や登記事項証明書なども活用し、所有者や隣接地の立会いのもと、境界線や地目(利用目的)の確認・特定を行います。高精度の測量器具(トータルステーションなど)を使用し、ミリ単位の精密な計測技術が求められる仕事です。
書類・図面作成
現地調査や測量結果をもとに、登記申請に必要な図面や関係書類(測量図、現況図など)をCADソフトで作成します。作成した図面は、法務局に提出する公式記録となります。
登記申請業務(代理業務)
所有者からの依頼を受けて、法務局に対し「表示に関する登記申請」を代理で行います。具体例は、土地の分筆・合筆、新築・増築等による建物表題登記や地目変更登記などです。これらの申請を正確かつ迅速に遂行し、不動産登記簿を更新します。
境界確定・立会い
隣接する土地の所有者との境界確認や立会い調整も重要な業務です。不動産取引や相続で境界トラブルが発生しやすいため、境界標を設置し、地積や筆界(公的な土地境界)を明確にします。
審査請求・筆界特定・ADR代理
登記申請への異議や境界紛争が発生した場合、審査請求や筆界特定(登記所による境界特定手続)の代理を行います。また、民事紛争調停(ADR)においても、法務大臣認定を受けた場合は弁護士と共同で代理が可能です。
関連業務
ほかにも公共事業に関する嘱託登記や地籍整備事業への関与など、官公署関連の依頼も増えています。
<業務の代表的な流れ>
土地家屋調査士の仕事の流れは、以下のようになります。
- 依頼受託~現地・資料調査
- 測量・調査の実施
- 図面・書類作成
- 隣接地立会・境界確定
- 登記申請手続き
- 完了書類納品・報酬受領
土地家屋調査士は「現地でのフィールドワーク+高度な法律・技術知識」が求められる士業であり、不動産取引や相続、開発などあらゆる場面で不可欠な専門職といえます。
土地家屋調査士資格の取得方法と難易度
次に、土地家屋調査士資格の取得方法と難易度について解説します。
資格の取得方法
土地家屋調査士試験に合格することが一般的な取得ルートです。学歴・実務経験などの制限はなく、誰でも受験できます。
例外として、法務省職員として一定年数勤務し認定を受ける方法もありますが、一般的ではありません。
試験の流れと科目
年1回、10月に筆記試験、翌1月に口述試験が実施され、筆記合格者のみ口述試験に進みます。
筆記試験は午前(法律・民法・不動産登記法・記述式)と午後(作図を含む実務系科目)で計200点満点です。
測量士・測量士補・一級または二級建築士の資格保有者は午前の部が免除されるため、受験生の9割以上は免除制度を利用しています。
受験申込・日程(2025年度例)
申込書配布:7月1日~8月8日(法務局・地方法務局で入手、郵送可)
申込期間 :7月28日~8月8日(窓口または郵送、インターネット申込は不可)
筆記試験 :10月19日
合格発表 :翌年1月7日(筆記)・2月13日(最終)
受験料 :8,300円(収入印紙)
試験合格後の流れ
合格後は土地家屋調査士会への登録、研修受講、諸費用の納付により資格が付与されます。
難易度と合格率
合格率は毎年8~9%程度と、士業資格の中でも高い水準です。
合格に必要な点数は、その年の難易度によって異なりますが、例年60~80%の得点が必要になる場合が多いです。
法律系と測量系双方の専門知識、現場での応用力、記述・作図の正確さが求められます。
合格までに必要な勉強時間は一般的に1,000時間前後、働きながら1~2年かけて挑戦するケースが多く見られます。
上記のように、土地家屋調査士資格は誰でも受験可能ですが、合格までには広範な法律・技術分野の知識、実践力と継続的な学習が不可欠で、難易度は高い国家資格です。試験科目の一部免除や対策講座・通信教育の活用も有効といえます。
土地家屋調査士が「やめとけ」や「きつい」と言われる理由5つ

土地家屋調査士が「やめとけ」や「きつい」と言われる理由には、以下のようなものがあります。
1.屋外での作業が厳しい
土地家屋調査士の現場業務は、屋外での測量・確認作業が主軸です。
真夏の酷暑や真冬の低温、雨・風・雪など過酷な天候下でも作業を中断できないことがあり、体力的な負担が非常に大きくなります。災害時や悪天候時の現場立会いも避けられず、熱中症や体調不良リスクも常につきまといます。
都市部でも狭小地や地形の悪い場所、山間部での作業も多く、重い測量機器や資材の持ち運びも伴うため、屋外業務の厳しさが「きつい」と言われる大きな理由です。
2.土日・時間外対応が多い
土地家屋調査士の業務は、現地作業だけでなく、隣接地所有者や依頼者との立会い・調整が重要です。
関係者の日程に合わせる必要があるため、平日日中だけでなく土日や早朝・夜間に現場作業や立会いが発生するケースが少なくありません。
特に繁忙期や年度末、法改正への対応が重なる時期は休日返上となることも多く、ライフワークバランスの確保が難しいという現実があります。
3.繁忙期がある
土地家屋調査士の仕事は、不動産の取引や相続などの需要によって、繁忙期と閑散期の差が大きくなります。
特に、年末年始や年度末などは登記の申請が急増するため、仕事量が多くなります。そのため、繁忙期には、早朝から深夜までの長時間勤務や、連日の残業が発生することもあるでしょう。
このような繁忙期の仕事は、精神的にも肉体的にも過酷と感じる方がおられます。
4.独立時の営業と経営の負担が大きい
土地家屋調査士は独立開業型の働き方が多い士業です。自ら事務所を構えた場合、測量・登記業務以外に営業活動や顧客開拓、経理・請求事務、スタッフのマネジメントなど、経営全般を担う負担が避けられません。
競合事務所との受注競争や価格交渉、案件の波による収入の不安定さも大きなストレスとなります。また、顧客からのクレームやトラブル対応まで一手に引き受ける必要があり、独立後の精神的・物理的負担が「やめとけ」と評される要因です。
5.立会いやトラブル時の精神的苦痛が大きい
境界確定作業や登記申請業務では、隣接地所有者との立会いや説明・調整が不可欠です。
境界を巡る主張の対立や感情的なトラブルも頻発し、クレーム対応や説得力ある説明、時に仲裁役としての高いコミュニケーション能力が求められます。人間関係の摩擦が精神的な重荷となりやすく、うまく進まない場合は業務が長期化することもあります。
こういった「人との軋轢」や社会的責任の重さがメンタル面での大きなコストとなっています。
以上のように、土地家屋調査士の仕事は、さまざまな理由から「やめとけ」や「きつい」と言われることがあります。しかし、これらのデメリットにもかかわらず、土地家屋調査士の仕事に魅力を感じる人も多くいます。
土地家屋調査士の仕事は、不動産のプロとして、社会に貢献することができるやりがいのある仕事です。また、独占業務であることや、独立開業がしやすいことなどのメリットもあります。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
土地家屋調査士の魅力と将来性

土地家屋調査士の魅力については、以下のようなものが挙げられます。
独占業務の強みがある
土地家屋調査士の最大の強みは「表示に関する登記」の独占業務にあります。
この業務は土地・建物の現況を正確に調査・測量し、その登記申請を行うものであり、法律で調査士以外にできないと定められています。
今後も不動産登記制度が続く限り、土地家屋調査士の仕事がなくなることは考えにくく、安定した将来性を維持しています。
独立・開業の可能性がある
土地家屋調査士は、自分の名前で業務を行える資格であり、独立開業することができます。独立開業すれば、自分のペースで仕事を進められるだけでなく、自分の得意分野や興味のある案件に特化したり、自分の価値観に合った仕事を選べたりするメリットがあります。また、独立開業すれば、自分の実力や努力に応じて収入を増やすことも可能です。
独立開業には事務所の開設や経営のノウハウなどの準備が必要ですが、その分、自分のやりたい仕事を実現できる魅力があります。
AI時代に揺るがない専門性
AI技術の進歩で多くの分野が自動化されつつありますが、土地家屋調査士は「現地での測量作業」「境界確定」「関係者間の交渉や調整」といった高度な専門知識と人間力を要する業務が中心です。
特に隣地所有者との立ち会いやトラブル調整など、AIが苦手とする「複雑なコミュニケーション」が避けて通れないため、AI化による代替リスクは低いとされています。
また、AIは事務作業や図面作成の支援で価値を発揮し、調査士の専門性をより高める役割を果たします。
相続や不動産市場の需要
高齢化社会の進展を背景に、相続をきっかけとした土地の分筆や権利移転、売却案件は今後さらに増加が見込まれています。
不動産売買・相続・空き家対策・所有者不明土地問題など、社会課題の解決には土地家屋調査士の存在が不可欠です。
また、長く未登記だった土地の再整理や、都市開発などのプロジェクトでも活躍の場が広がっています。
業界の高齢化と新規参入のチャンス
土地家屋調査士業界は、登録者の約半数が60代以上と高齢化が顕著で、今後大量の引退が予想されます。業界の新陳代謝が進むため、若手や新規参入希望者には非常に大きなチャンスの時代です。
競合が多い士業分野でありながら、参入障壁(資格試験・実務経験・開業資金)が高く、急激な供給過多の心配も少ないとされています。
地道な実務経験と最新スキルを身に付けることで、安定したキャリア形成が期待できます。
このように、相続に関する業務は土地家屋調査士の仕事の中でもやりがいのあるものであり、将来性の高いものです。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
土地家屋調査士の年収実態

次に、土地家屋調査士の年収について解説します。
平均年収と地域差
土地家屋調査士の平均年収は、約500万円~600万円程度と言われています。これは、日本の平均年収(約 433万円 )よりも高い水準です。
年齢・経験年数に応じて収入が上がる傾向が明確で、20代~30代前半は350万~600万円、40代は650万~750万円、50代では800万~900万円台が平均値の目安です。特に50代は経験・人脈・実績が充実し年収ピークを迎えますが、60代以降は体力や案件減少でやや下がる傾向も見られます。
| 年代 | 年収目安 |
|---|---|
| 20~29歳 | 350万~500万円 |
| 30~39歳 | 500万~650万円 |
| 40~49歳 | 650万~800万円 |
| 50~59歳 | 750万~900万円 |
| 60代以降 | 600万円前後 |
地域別に見ると、東京都が最も高く、千葉県や神奈川県などの関東エリアが比較的高めです。一方、福岡県が最も低くなっており、地方エリアは平均すると低い傾向にあります。
このことから、住宅数や企業数の多い地域は仕事が豊富にあるため、給料も高いと言えるでしょう。
土地家屋調査士の収入を左右する要因
土地家屋調査士の収入は、主に以下の要因によって左右されます。
独立・雇われの違い
土地家屋調査士が独立・開業した場合には、年収ベースで約800万円~1,000万円以上稼げる可能性があります。仕事を受注すればそれだけ年収が上がりますが、実力と営業努力に依存します。なお、雇われている場合は約400万円~600万円程度が一般的です。
年齢・経験・役職の違い
土地家屋調査士は、年齢と経験を重ねることで、年収が上がる傾向にあります。特に40代から50代は、役職に付いたり独立開業したりするケースが多く、年収が約700万円~900万円になることもあります。一方、60代になると退職後再雇用や自分のペースで働くケースが多くなり、年収は約600万円~650万円程度に下がるのが一般的です。
企業規模の違い
大企業は大規模な公共工事を手掛けることがあるため、プロジェクト全体を管理する建設コンサルタントの立場で働く機会があります。そのため、1,000万円付近まで年収を伸ばすことも可能です。一方、中規模企業では、720万円程度が一般的な年収額です。
収入アップのポイント
土地家屋調査士として年収を上げるには、次のような戦略が有効です。
- スキル・経験の向上:専門領域の習得や難易度の高い案件に挑戦することで単価アップ。
- ダブルライセンス・関連資格の取得:測量士など他資格を取得すると受託分野が増え、案件獲得競争力が上がる。
- 都市部への進出・地域選定:大都市圏の事務所開設で高単価案件・件数増加が見込めます。
- 営業力・マネジメント強化:リピーター獲得や法人・公共案件の開拓、スタッフ教育で受注規模拡大。
- IT・プロジェクト管理効率化:図面作成や顧客管理システムの導入で生産性を高めることも報酬増加につながります。
土地家屋調査士は平均して高水準の年収が実現しやすい士業ですが、働き方・経営力・地域・キャリア戦略によって大きな収入幅が生じます。長期的な視点とスキルアップを意識した活動で、更なる年収アップも十分可能な分野です。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
土地家屋調査士に必要な資格と取得方法

次に、土地家屋調査士に必要な資格と取得方法を解説します。
必要な資格と試験内容
土地家屋調査士になるためには、法務省が主催する国家試験に合格して、土地家屋調査士資格を取得しなければなりません。土地家屋調査士資格の試験は、筆記試験と口述試験の2回に分けて実施されます。
筆記試験は、午前の部と午後の部に分かれており、午前の部では平面測量と作図に関する問題が、午後の部では不動産登記法や民法などの法律問題が出題されます。筆記試験に合格した人だけが口述試験に進める仕組みです。
口述試験は、筆記試験の内容に加えて、土地家屋調査士法や測量法などの法令や、測量技術や登記業務に関する知識や技能が問われます。口述試験に合格すると、土地家屋調査士として登録可能です。
試験の難易度と合格率
土地家屋調査士試験は、非常に難易度の高い試験と言われており、近年の合格率は8%~9%という低い水準で推移しています。
合格するために必要な勉強時間は、約700~1,000時間が目安とされており、1年~2年ほどの期間をかけて受験勉強に励むケースが一般的です。
なお、測量士、測量士補、一級・二級建築士のいずれかの資格を有している場合、筆記試験の午前の部が免除されるため、難易度は大きく下がります。そこで、取得難易度の低い測量士補の資格を先に取得し、免除要件を満たしてから、土地家屋調査士試験に臨む受験者の方が多いようです。
土地家屋調査士の日常業務

以下では、土地家屋調査士の日常業務について解説します。
土地家屋調査士の1日の業務の流れ
土地家屋調査士の1日の業務の流れは、事務所での作業と現場での作業に分けられます。
事務所での作業は、依頼者との打ち合わせや見積もり作成、登記申請書類の作成や提出、測量データの整理や分析などです。
一方、現場での作業は、土地や建物の測量や調査、筆界の確認や特定、関係者との協議などです。
一日の業務の流れは、依頼内容や進捗状況によって異なりますが、一例としては以下のようになります。
朝の仕事
事務所に出社し、メールや電話での問い合わせや依頼の対応、当日のスケジュールの確認、必要な資料や機材の準備などを行う。
午前中の仕事
現場に移動し、測量や調査を行う。
測量は、測量機器やGPSを使って土地や建物の位置や形状、面積などを正確に計測する作業です。調査は、法務局や市役所などで登記情報や地図、土地台帳などの資料を閲覧したり、現地の状況や隣接所有者の意見などを確認したりする作業です。
昼の仕事
現場近くで昼食をとる。その後、測量や調査の結果を確認し、問題点や改善点などを検討する。
午後の仕事
現場での作業を続けるか、別の現場に移動して作業を行う。また、依頼者や関係者との打ち合わせや協議を行うこともある。
打ち合わせや協議では、測量や調査の結果や進捗状況、登記申請の手続きや費用などについて説明したり、質問や要望に答えたり、意見や提案を交換したりする。
夕方の仕事
事務所に戻り、現場での作業の報告や記録、登記申請書類の作成や提出、測量データの整理や分析などを行う。また、翌日のスケジュールの確認や準備などを行う。
夜の仕事
事務所を退社し、自宅に帰る。また、自宅では、勉強や研修、資格更新などのための時間をとることもあります。
土地家屋調査士のケーススタディ
土地家屋調査士のケーススタディには、さまざまなものがありますが、一例としては以下のようなものが挙げられます。
筆界が不明確な土地の測量や調査
筆界が不明確な土地とは、境界標がなかったり、登記情報と現況が異なっていたりする土地のことです。このような土地の測量や調査は、過去の資料や隣接所有者の証言などをもとに、筆界の推定や特定を行う必要があります。
しかし、資料が不足していたり、証言が一致しなかったりする場合もあり、正確な筆界の確定には困難が伴います。そのため、関係者との協議や調停などを通じて合意に基づく筆界の決定を目指すのも、土地家屋調査士の仕事です。
新築建物の登記申請の代理
新築建物の登記申請の代理とは、建物を新しく建てた場合に、その建物の表示に関する登記を依頼者に代わって行うことです。この業務では、建物の位置や形状、構造、階数、面積などを測量や調査によって正確に把握し、登記申請書類を作成し、法務局に提出する必要があります。
しかし、建物の形状が複雑だったり、隣接する建物との距離が近かったりする場合は、測量や調査が難しくなります。そのため、測量機器やGPSなどの最新の技術を駆使して建物の状況を正確に把握するのも、土地家屋調査士の仕事です。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
今すぐ応募できる求人はこちら
\非公開求人/
雇用形態:正社員
売買仲介営業
20代年収800万円
到達者多数
月収:25万円~
賞与:インセンティブ(毎月支給)
勤務地:東京都23区
必須条件:20代未経験OK
- 備考:
- 週休二日制(水・土)
\非公開求人/
雇用形態:正社員
賃貸仲介営業
20代年収700万円
到達者多数
月収:27万円~
賞与:インセンティブ(年4回)
勤務地:東京都23区
必須条件:20代未経験OK
- 備考:
- 完全週休二日制(水・木)
\非公開求人/
雇用形態:正社員
投資用不動産営業
20代年収1000万円
到達者多数
月収:24万円~
賞与:インセンティブ(年2回)
勤務地:東京都
必須条件:20代未経験OK
- 備考:
- 週休二日制(水・土)
\非公開求人/
雇用形態:正社員
用地仕入れ営業
20代年収1000万円
到達者多数
月収:25万円~
賞与:インセンティブ(年2回)
勤務地:東京都
必須条件:20代未経験OK
- 備考:
- 週休二日制(水・木)
土地家屋調査士に向いている人の特徴と失敗しないためのポイント
以下では、土地家屋調査士に向いている人・失敗しないためのポイントについて解説します。
適性やスキル
土地家屋調査士に向いている人は、まず「正確な作業が得意」であることが重要です。測量や登記は法律・技術両面で細かなミスが許されないため、注意力と慎重さが求められます。
また、現場での作業が多いため、ある程度の体力や屋外活動に耐えうる健康状態も必要です。さらに、隣地所有者や依頼者、役所担当者との粘り強いコミュニケーションが不可欠であり、人間関係調整や説明・説得力も活かされます。
CADや測量機器のITスキル、現場判断力、独立開業を目指す場合は経営感覚も重要です。
やりがいと社会的価値
土地家屋調査士は、不動産の権利明確化や法的安全性を担う「社会インフラの守り手」として高い社会的価値を持つ専門職です。調査・測量結果が登記情報となり、人々の安心な土地活用や財産権を支えます。
また、相続や不動産売買など人生の節目に深く関わり、トラブル解決やまちづくりにも貢献できます。AIが代替できない現場力や交渉力を発揮し、目に見える成果を実感できるのも大きなやりがいです。
廃業リスクと対策
土地家屋調査士は独立型士業のため、顧客獲得や事務所経営がうまくいかないと廃業リスクも生じます。業界の高齢化・案件の波・競争激化、景気や法改正による受注減少も注意点です。
失敗しないためには、現場経験を積みつつ専門性と人脈拡大、ダブルライセンス(測量士・行政書士等)取得やIT活用で仕事の幅を広げましょう。継続的に営業・広報活動や顧客満足度向上にも力を入れ、経営や法改正の情報収集・自己研鑽を怠らない姿勢が安定経営のカギです。
このように、土地家屋調査士は「緻密な作業力」「対人調整力」「自己管理・経営力」をバランス良く備えた人に特に向いています。現場と社会をつなぎ、長期的にキャリア活用できる可能性が広い職種です。
土地家屋調査士のキャリアパス

以下では、土地家屋調査士のキャリアパスについて解説します。
資格取得後のキャリアパス
土地家屋調査士になるには、法務省が主催する国家試験に合格して、資格を取得する必要があります。前述の通り、土地家屋調査士の試験は非常に難しく、合格率は8%~9%という低い水準です。
資格を取得した後は、土地家屋調査士事務所や測量会社などに勤めて、実務経験を積むのが一般的です。勤務先によっては、測量士や建築士などの他の資格も取得することも可能です。
また、数年程度の実務経験を積んだ後は独立開業することも可能です。独立開業する場合は、自分で営業や顧客開拓を行う必要がありますが、収入や仕事の幅を広げることができるでしょう。
独立開業後のキャリアパス
独立開業した土地家屋調査士は、個人事業主としてさまざまな案件に対応することが可能です。
案件の種類には、以下のようなものがあります。
- 個人の依頼:土地や建物の登記申請、境界確定、分筆合筆、相続登記など
- 企業の依頼:開発や分譲地の測量や登記、マンションや商業施設の登記、測量図の作成など
- 行政の依頼:公図の作成や更新、地籍調査、境界鑑定、筆界調査など
独立開業した土地家屋調査士の収入は、依頼内容や規模、地域などによって大きく変わりますが、平均年収は約 800万円~1,000万円程度と言われています。さらに、大手デベロッパーや公共工事などの大規模な案件を受けることができれば、年収が2,000万円以上になることもあります。
弊社では、数多くの方にフリーランス案件を獲得していただいています。ビーバーズフリーランスでは、以下のような案件を豊富に抱えています。
- 週2.3日から選択できる幅広い案件
- 月60万円~70万以上の高収入案件多数
- 無料登録から最短1日でお仕事紹介
まずは無料登録をして色々な求人・案件を見てみてください。専門エージェントからおすすめの求人・案件をご紹介することも可能です。
土地家屋調査士のまとめ
このように、土地家屋調査士は難易度が高くてきつい仕事である反面、年収が高く、多様なキャリアパスのある魅力的な仕事でもあります。実際に、土地家屋調査士の資格を取得して独立・開業に成功すれば、年収2,000万円以上稼ぐことも可能です。
そこで、このような特徴から、土地家屋調査士への就職や転職を考える際は、本当にご自分に合う仕事かどうかの分析を行い、自身の適性を十分に理解してから就職や転職活動を行うことが重要です。
転職エージェントのサポートを受けながら転職活動を進められれば、転職に関する悩みを解消できるだけでなく、自己分析やヒアリングをとおして自分の向いている仕事に気付けるかもしれません。
特化型の転職エージェント「ランダーズ」では、自己分析のサポートをしながら、あなたに合った転職先を提案いたします。
まずはお気軽に登録して、転職に関する悩みや疑問を相談してください。