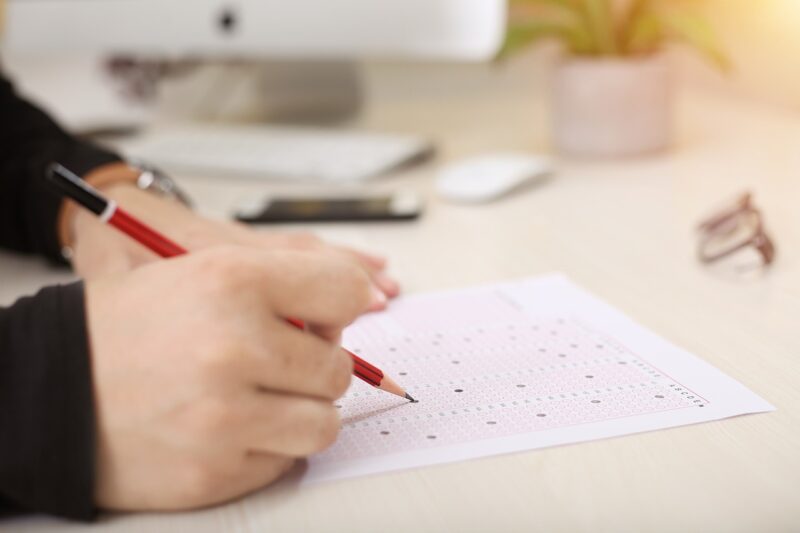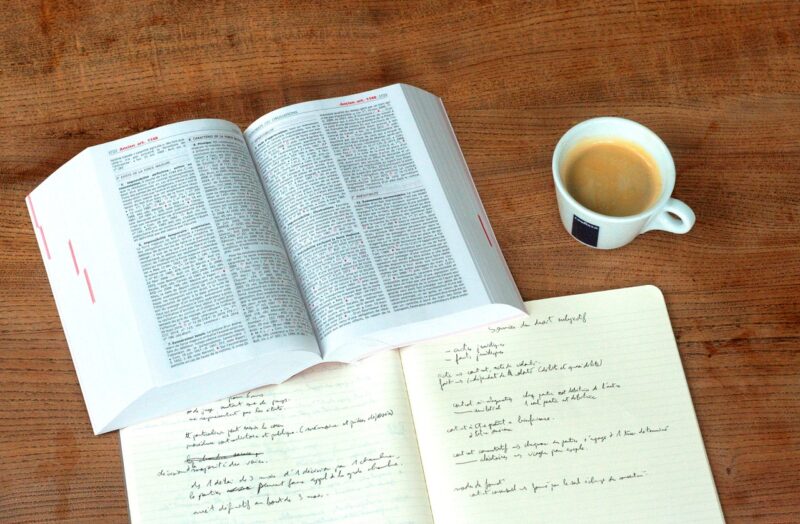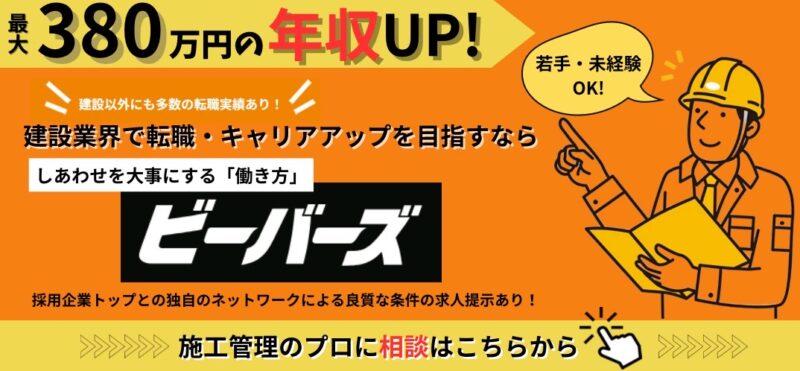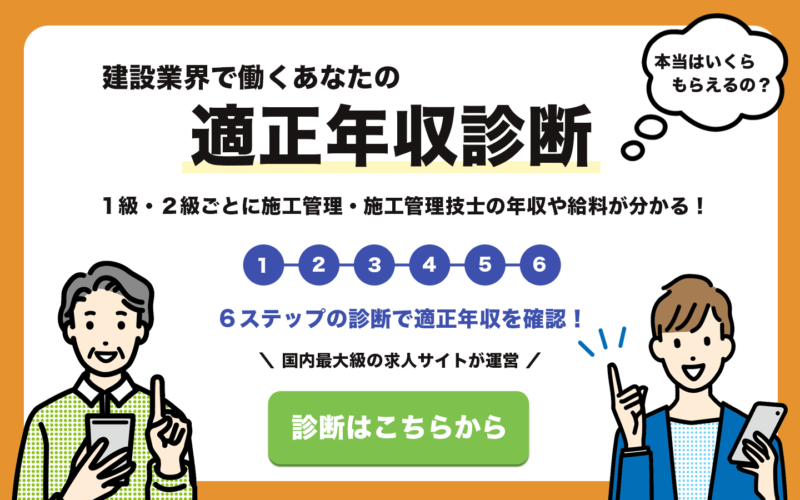施工管理技士資格の 受験資格を確認しよう!
【令和6年度改正】施工管理技士の受験資格の変更内容や注意点を徹底解説
建設 働き方やキャリア 転職 建設業界動向・情報 施工管理令和6年度の施工管理技士試験では、受験資格が大幅に改正され、これまでの要件が見直されました。
特に第一次検定の受験資格が緩和され、より多くの人が挑戦しやすい環境が整いました。
しかしその一方で、改正に伴う注意点や実務経験の証明方法など、事前に把握しておくべきポイントも増えています。
そこで本記事では、改正内容を具体的に解説し、どのような準備が必要かを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
令和6年度の施工管理技士の受験資格改正の概要
受験資格改正の背景と目的
建設業界では高齢化が進み、中長期的な担い手の確保・育成が課題となっています。
この状況を改善するため、令和6年度から施工管理技士の受験資格が改正されました。
受験資格改正の主な目的は、若年層や未経験者などの多様な人材の参入を促進し、1級施工管理技士の育成を加速させることです。
従来の制度では、1級資格の取得までに時間がかかりすぎるという問題がありました。
そこで、第一次検定の受験資格を緩和し、より早期から高度な技術者育成を可能にする一方で、第二次検定の受験資格を厳格化することにより、実務経験に基づく確かな技術力の確保を目指しています。
新旧制度の主な変更点
上記の新制度では、第一次検定の受験資格が大幅に緩和されています。
1級は19歳以上、2級は17歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく受験できるようになりました。(2級は従来と変更なし)
一方、第二次検定は第一次検定合格が必須条件となり、その後1〜5年の実務経験が必要です。
実務経験の範囲も明確化され、検定種目に対応した建設業の種類に該当する工事が対象です。また、複数の検定種目に対応する工事経験は、同じ経験を複数の検定種目の実務経験として申請できるようになりました。
改正による受験者への影響
今回の改正により、受験者に次のような影響が出ています。
受験者層の拡大
1級の第一次検定は年齢要件のみとなったため、実務経験や学歴に関係なく多くの人が受験できるようになりました。
例えば、令和6年度は受験者数が前年比1.5倍以上に増加し、合格者も大幅に増えています。
試験対策の難易度変化
二次試験では「暗記」中心から「与えられた工事概要をもとに考察・提案する」出題形式に変わり、実践的な思考力や応用力がより重視されるようになりました。
一次試験の出題形式変更により、従来の対策方法が通用しない部分も出てきており、受験者は新形式に合わせた準備が必要です。
経過措置による柔軟な対応
令和10年度までは旧制度・新制度の選択が可能なため、現行受験者は自身の状況に応じて有利な制度を選択できます。
キャリア形成の早期化
若年層が早期に資格取得を目指せるため、キャリア形成のスピードが上がり、将来的な現場リーダーの早期育成が期待されています。
このように、令和6年度の改正は受験者の裾野を広げるとともに、より実践的な技術者の育成を目指す内容となっています。
関連記事:【令和6年度試験制度改訂版】施工管理技士資格の難易度ランキング|合格率や偏差値まで徹底解説
第一次検定の受験資格の変更要件
以下では、令和6年度から施行される施工管理技士の新しい受験資格要件について、第一次検定の主な変更点を解説します。
| 区分 | 1級施工管理技士 | 2級施工管理技士 |
|---|---|---|
| 年齢制限 | 19歳以上(当該年度末時点) | 17歳以上(当該年度末時点) |
| 学歴要件 | 撤廃 | 撤廃 |
| 実務経験要件 | 撤廃 | 撤廃 |
年齢要件の緩和
令和6年度の改正により、施工管理技士試験の第一次検定は「年齢要件のみ」で受験できるようになりました。
1級は受験年度末時点で19歳以上、2級は17歳以上であれば、学歴や実務経験を問わず誰でも受験可能です。
この改正は、若手技術者の早期育成や建設業界への参入促進を目的としています。
学歴や実務経験の要件の見直し
従来は、学歴や実務経験年数によって細かく受験資格が設定されていました。
例えば、大学の指定学科卒業なら3年、その他の学科や高校卒業の場合はさらに長い実務経験が必要でした。
しかし、令和6年度からはこうした学歴や実務経験の要件が撤廃され、年齢要件のみで受験できるように大幅に緩和されました。
新しい受験資格の詳細
1級第一次検定は、受験年度末時点で19歳以上であれば、学歴や実務経験を問わず受験可能です。
2級第一次検定は、受験年度末時点で17歳以上であれば、学歴や実務経験を問わず受験可能です(この点は以前から変更なし)。
この新制度により、1級・2級ともに第一次検定の合格後は「施工管理技士補」として認定され、就職や転職でも有利に働きます。ただし、施工管理技士(正式資格)となるためには、引き続き第二次検定の合格と所定の実務経験が必要です。
この改正により、より多くの若手や未経験者が早期に資格取得へ挑戦できるようになり、建設業界全体の人材確保と技術者育成の加速が期待されています。
第二次検定の受験資格と実務経験の注意点
以下では、第二次検定の受験資格と実務経験について、詳しく解説します。
第一次検定合格の必須条件
令和6年度以降、第二次検定を受験するためには、第一次検定合格が必須条件となりました。ただし、令和3年度以降の第一次検定合格が対象となります。
実務経験の定義と範囲
実務経験とは、建設工事の施工に直接的に関わる技術上の職務経験を指します。
第二次検定を受験する際の実務経験は、原則として「建設業法に規定される該当業種の工事」での経験が対象となります。
証明方法は、工事ごとに工事請負者の代表者や監理技術者など、現場を管理する立場の者による証明が必要です。
なお、令和6年3月31日までに従事した工事については、従前の方法(所属会社の代表者等による証明)も認められています。
具体的には以下の表のような工事種別が対象となります。
| 工事種別 | 主な工事内容 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 事務所ビル建築工事、共同住宅建築工事 等 |
| 大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 等 |
| とび・土工・コンクリート工事 | とび工事、足場仮設工事、囲障工事、(PC、RC、鋼)杭工事、コンクリート工事 等 |
- 受注者(請負人)として施工を指揮・監督した経験
- 発注者の下で監督・検査に従事した経験
- 建設工事の施工に関する技術上の指導監督的な立場で従事した経験
特定実務経験の要件
特定実務経験とは、通常の実務経験に加えて「建設業法適用の請負金額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)」の大規模工事で、監理技術者や主任技術者(またはその指導下)として施工管理に従事した経験を指します。
特定実務経験が必要な場合、1年以上この条件を満たす必要があります。
具体的には、下記いずれかの経験が求められます。
- 当該工事種別の監理技術者資格者証を有する監理技術者または主任技術者の指導下で行った施工管理
- 自ら監理技術者または主任技術者として行った施工管理
この特定実務経験は、通常の実務経験年数に含めて計上できます。
複数業務従事時の経験計算方法
複数の検定種目に対応する建設業の種類の工事経験については、同じ経験を複数の検定種目の実務経験として申請することが可能です。
ただし、異なる検定種目にかかる複数の工事を担当していて期間に重複がある場合、重複部分を二重に計上することはできません。重複部分における実務経験の計算は、実際の工事の従事割合(例えば日数等)に応じて按分する必要があります。
例えば、ある期間に建築工事と電気工事を並行して行っていた場合には、
重複期間の従事割合を建築2:電気工事1と算定できる場合に、4ヶ月の重複期間があったとすると、
- 建築の実務経験:4ヶ月 × (2/3) ≈ 2.67ヶ月
- 電気工事の実務経験:4ヶ月 × (1/3) ≈ 1.33ヶ月
と計算します。
なお、令和10年度の試験までは、第二次検定に関しては新旧どちらの受験資格でも受験が可能です。
経過措置期間中の選択肢
令和6年度から令和10年度までの経過措置期間中は、「新受験資格」と「旧受験資格」のいずれかを選択して第二次検定を受験できます。
- 旧受験資格:学歴や職歴に応じて必要な実務経験年数が異なります(例:大学指定学科卒は3年、高卒は最大11年6ヵ月など)。
- 新受験資格:第一次検定合格後に一定期間の実務経験(1級は1年以上、2級は3年以上など)を積めば受験可能です。
この期間中に有効な第二次検定受験票を取得した場合、経過措置期間後も再受験が可能です。
ただし、令和11年度(2029年度)以降は新受験資格のみが適用され、旧受験資格での受験はできなくなります。
このように、第二次検定の受験資格は実務経験の証明方法や特定実務経験の要件が明確化され、経過措置期間中は新旧どちらの制度も選択できる柔軟な運用となっています。
【未経験者向け】職種を変える前に適職診断をしておこう
施工管理技士は、建設業界の知識だけでなく施工管理としての適性が求められる仕事でもあります。
そのため、施工管理技士になる前に適性を確認しておくことがおすすめです。
無料の適職診断ツールを使えば、施工管理への適性を確認することができます。
まだやっていない人は今すぐ診断をしましょう。
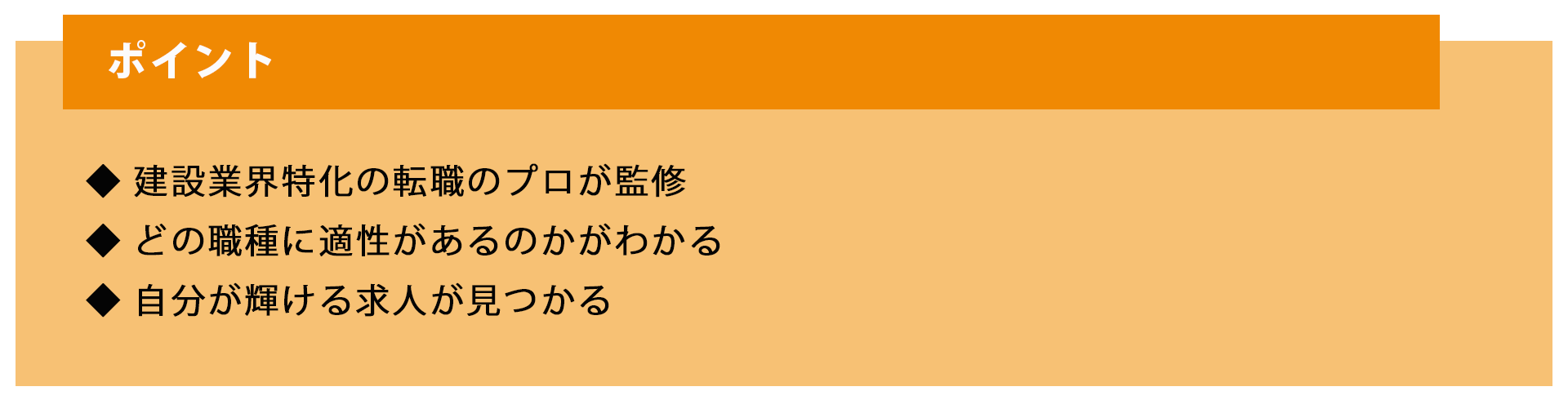
診断は16タイプ診断に基づいています。 本格的にキャリアを考える前に適性を確認して、より自分の得意な分野でキャリアアップをしましょう!
実務経験の証明方法
実務経験を証明するためには、所定の「実務経験証明書」を提出する必要があります。この証明書には以下の情報を記載します。
- 工事種目:土木、建築、電気など具体的な種類。
- 職名と役割:工事主任や施工担当など役職名と具体的な業務内容。
- 勤務先情報:法人名、所在地、代表者氏名。
- 実務期間:従事した期間を年・月単位で記入。
証明書は勤務先の代表者による署名が必須です。また、確認資料(契約書や請求書など)を添付して実際に行われた工事であることを証明します。
これらは国土交通省や自治体が指定する様式を使用し、不備がないよう正確に記入する必要があります。
複数の検定種目への申請可能性
新制度では、同じ工事経験を複数の検定種目に対して申請することが可能です。
例えば、1つの工事が「土木一式工事」と「舗装工事」の両方に該当する場合、それぞれの検定種目で実務経験として申請できます。
ただし、以下のルールに注意が必要です。
- 同時期に複数の業務に従事した場合、その期間は重複して計上できません。
- 重複期間については従事割合を按分して算出します(例:全体期間を3:2で分割)。
- 同一勤務先かつ同一業種の場合は、1年以内であればまとめて申請可能です。
この改正により、多様な業務経験を効率的に活用できるようになり、受験者にとって柔軟性が拡大しました。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
旧制度から新制度への移行期間
令和10年度までの経過措置
令和6年度から令和10年度までの5年間は、施工管理技士の受験資格に関する経過措置期間となっています。この期間中は、第二次検定については新旧どちらの受験資格でも受験が可能です。
さらに、令和10年度までに有効な第二次検定受験票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き旧制度の実務経験要件で第二次検定の受験が可能となります。
この経過措置により、受験者は新旧両方の制度を活用して受験戦略を立てることができます。
旧制度での受験資格の有効期限
旧制度での受験資格の有効期限は、資格種別によって異なります。
2級建築施工管理技士の場合、令和3年の試験制度改正以降、第一次検定(旧:学科試験)合格の有効期限はなくなりました。
一方、旧2級学科試験合格者については、従来通り合格年度を含む12年以内かつ連続2回に限り、当該第二次検定を制度改正前の資格要件で受験できます。
1級建築施工管理技士については、令和10年度までに有効な第二次検定受験票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き受験が可能です。
新旧制度の併用期間における注意点
新旧制度の併用期間である令和6年度から令和10年度までは、受験者にとって戦略的に重要な時期となります。なぜなら、この期間中は現在の実務経験を活かして旧制度で受験するか、新制度に基づいて受験するかを選択できるからです。
特に、現在実務経験がある方や令和10年度までに実務経験が発生する方は、令和10年度までに第二次検定を受験しておくことが重要です。
令和11年度以降は、第一次検定合格後に新たに実務経験(原則として5年以上)を積まないと第二次検定を受験できなくなるため、旧制度での受験機会を逃さないよう注意しましょう。
受験資格改正によるメリットと課題
以下では、この受験資格改正によるメリットと課題、注意点を解説します。
受験者にとってのメリット
令和6年度の改正により、1級第一次検定が19歳以上で実務経験不要となったことで、若年層が早期に資格取得に挑戦できる環境が整いました。
第一次検定合格後は「施工管理技士補」として認定され、就職や転職時に優遇されるだけでなく、第二次検定合格までの実務経験期間が短縮されます(例:1級技士補は3年→1年)。
また、経過措置期間(令和10年度まで)は旧制度と新制度を選択可能で、既存の実務経験を活用できる柔軟性も特徴です。これにより、未経験者でも早期にキャリア形成を開始でき、現場リーダー育成の加速が期待されます。
加えて、複数業種の実務経験を重複申請可能となり、異なる検定種目への挑戦が容易になりました。
実務経験証明の課題
第二次検定では、工事ごとに請負者の代表者または監理技術者による証明が必要で、特に特定実務経験(請負金額4,500万円以上の大規模工事)は厳格な審査が求められます。
発注者支援業務での経験は特定実務経験として認められず、監理技術者・主任技術者の指導下での実績のみが有効です。
中小企業の受験者は大規模工事の経験機会が少なく、証明書類の収集が困難になるケースも想定されます。
さらに、複数企業での経験がある場合、各企業から個別に証明書を取得する必要があり、手続きの煩雑さが課題です。
試験準備における注意点
第一次検定の出題形式が変更され(例:1級建築施工管理技士は「五肢二択」→「五肢択一」)、暗記中心から応用力重視へ移行しています。
第二次検定では「与えられた工事概要の分析」が求められ、実務経験に基づく計画書作成能力が問われるため、過去問だけでは対応が困難です。
特定実務経験の不足を補うためには、監理技術者との連携や大規模工事への参画機会を積極的に確保する必要があります。
経過措置期間中は新旧制度の違いを理解し、自身の実務経験に適した受験戦略を選択することが重要です。
上記のように、今回の改正により若手の早期参入が促進される一方、実務経験証明の厳格化や試験難易度の変化が課題です。そのため、受験者にとっては工事規模・証明方法の確認と新形式への対応強化が急務となります。
今すぐ応募できる求人はこちら
\非公開求人/
雇用形態:正社員
準大手ゼネコン各種施工管理
年収560万円~
月収:40万円~
賞与:2ヶ月分
勤務地:全国(希望の支店)
必須条件:2級以上建築施工管理技士
- 備考:
- 転勤なし
退職金制度あり
\非公開求人/
雇用形態:正社員
大手ゼネコン各種施工管理
年収800万円~
月収:50万円~
賞与:4ヶ月分~
勤務地:全国(希望の支店)
必須条件:1級建築施工管理技士
- 備考:
- 転勤なし
退職金制度あり
\非公開求人/
雇用形態:正社員
新築住宅の建築施工管理
年収532万円~
月収:38万円~
賞与:2ヶ月分
勤務地:全国(希望の支店)
必須条件:未経験OK
- 備考:
- 転勤なし
退職金制度あり
\非公開求人/
雇用形態:派遣
地域密着型建設会社の建築施工管理
年収460万円~
月収:38万円~
昇給:あり
勤務地:東京23区内の現場
必須条件:未経験OK
- 備考:
- 長期契約・契約更新可
\非公開求人/
雇用形態:派遣
準大手サブコンの設備施工管理
年収540万円~
月収:45万円~
昇給:あり
勤務地:全国(希望の現場)
必須条件:2級以上管工事または電気工事施工管理技士
- 備考:
- 長期契約・契約更新可
\非公開求人/
雇用形態:業務委託
住宅中心の太陽光発電設置工事
単価45万円~
単価:45万円~
勤務地:埼玉県全域
募集職種:太陽光発電設置工事
\非公開求人/
雇用形態:業務委託
集合住宅のアフターメンテナンス
単価40万円~
単価:40万円~
勤務地:福岡県博多市
募集職種:太陽光発電設置工事
\非公開求人/
雇用形態:業務委託
新築住宅中心の意匠設計
単価42万円~
単価:42万円~
勤務地:東京23区
募集職種:意匠設計
施工管理技士試験内容の変更点
試験形式の変更(五肢択一への移行)
令和6年度から施工管理技士試験の形式が大きく変更され、「五肢択一」方式が追加導入されました。
従来の「五肢二択」や「四肢択二」から移行したことで、試験の難易度と評価方法に影響が出ています。
1級土木施工管理技士試験では、問題数が5問増加し、全て必須問題となりました。2級建築施工管理技士試験でも、「能力問題」が4問から5問に増え、五肢択一形式になりました。
この変更により、受験者は各問題に対してより慎重に選択肢を検討する必要があり、幅広い知識と正確な判断力が求められるようになっています。
出題範囲の見直し
試験の出題範囲が拡大され、より幅広い知識が要求されるようになりました。
1級土木施工管理技士試験では、新たに土質力学、水理力学、構造力学の分野から問題が出題されるようになりました。特に構造力学では、曲げモーメントや図心を求める問題など、より高度な内容が含まれています。
1級建築施工管理技士試験では、建築の基礎、構造、材料に関する問題が必須となり、苦手分野を避けることができなくなりました。
これらの変更により、受験者は従来の過去問学習だけでなく、新たな分野の勉強が必要となり、より総合的な知識が求められるようになっています。
合格基準の変更は?
合格基準に関しては、大きな変更は報告されていません。しかし、試験形式の変更に伴い、実質的な難易度に影響が出ています。
1級建築施工管理技士試験では、応用力を問う問題の足切り条件が緩和されました。従来の「5肢2択で4/6問正解」から「5肢1択で6/10問正解」に変更され、より柔軟な対応が可能となっています。
一方、問題数の増加により、合格に必要な正答数が増えています。例えば、1級土木施工管理技士試験では問題数が5問増えたため、60%という合格基準は変わらないものの、合格に必要な正答数は増加している状況です。
これらの変更により、受験者はより幅広い知識と正確な判断力が求められるようになっています。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
新制度導入による建設業界への影響
受験者数の予測と変化
新制度の導入により、施工管理技士試験の受験者数は大幅に増加すると予測されています。これは、第一次検定の受験資格が年齢制限のみとなり、学歴や実務経験の要件が撤廃されたことで、より多くの人が受験できるようになったからです。
特に、若年層や建設業界への新規参入を考えている人々にとって、受験のハードルが下がったと言えるでしょう。
また、施工管理技士補の資格が設けられたことで、段階的なキャリアアップが可能となり、より多くの人が資格取得を目指すようになると考えられます。
関連記事:施工管理技士補とは?仕事内容や一級と二級の違い、試験の概要を徹底解説
若手技術者の参入機会の拡大
新制度の導入により、若手技術者の建設業界への参入機会が大きく拡大しています。
施工管理技士補の資格を取得することで、早い段階から監理技術者の補佐として現場に携わることができるようになりました。これにより、若手技術者は実務経験を積みながら、より高度な資格取得を目指すことができます。
また、新規学卒者の入職数が増加傾向にあり、2022年には4万3,000人にまで増加している状況です。
この傾向は、建設業界の魅力向上と若手の活躍の場の拡大によるものと考えられます。
建設会社の人材育成戦略への影響
新制度の導入は、建設会社の人材育成戦略にも大きな影響を与えています。
施工管理技士補の制度により、若手技術者を早期から現場に配置し、実践的な経験を積ませることが可能となりました。これにより、会社は長期的な視点で人材を育成し、段階的にスキルアップさせる戦略を立てやすくなっています。
また、監理技術者の負担軽減や業務の効率化が図れるため、より多くの現場を管理できるようになり、会社全体の生産性向上にもつながっている状況です。
さらに、若手の活躍の場が増えることで、建設業界全体の魅力向上にも寄与し、人材確保にも好影響を与えると期待されています。
弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。
- 完全週休2日制の求人
- 年収800万~900万以上の高収入求人多数
- 50代60代70代の方でも応募可能な求人
- 無料登録から最短1週間で転職可能
まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。
施工管理技士試験の受験資格改正のまとめ
今回の記事では施工管理技士資格の受験資格を中心のテーマとして、ご説明させていただきました。
建設業界でのキャリアアップ、収入アップ、転職活動における好条件獲得を考えている方にとって、資格は必須です。
また現在、施工管理技士不足は建設業界全体の課題ですので、取得を目指す資格としてお勧め資格であることは間違いありません。
転職エージェントのキャリアコンサルタントのサポートを受けながら就職や転職活動を進められれば、転職に関する悩みを解消できるだけでなく、自己分析やヒアリングを通して自分の向いている仕事に気付けるかもしれません。
特化型の転職エージェントである「ビーバーズ」は、自己分析のサポートをしながら、あなたに合った就職・転職先を提案いたします。
まずはお気軽に登録して、転職に関する悩みや疑問を相談してください。
【建設業界で転職を考えている方向け】無料診断ツール一覧
-
①適正年収診断
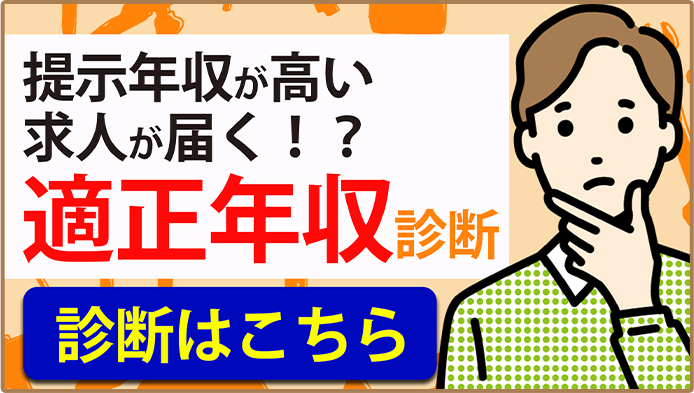
質問に答えていくだけであなたの市場価値がわかります。
無料で提示年収の高い求人をお届けします。 -
②ブラック企業診断
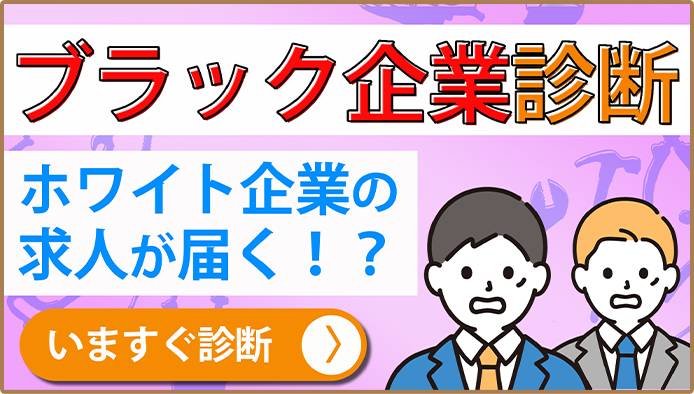
約40,000人の転職相談記録を元にあなたの在籍企業のブラック度を診断し、無料でホワイト企業の求人をお届けします。
-
③適職診断
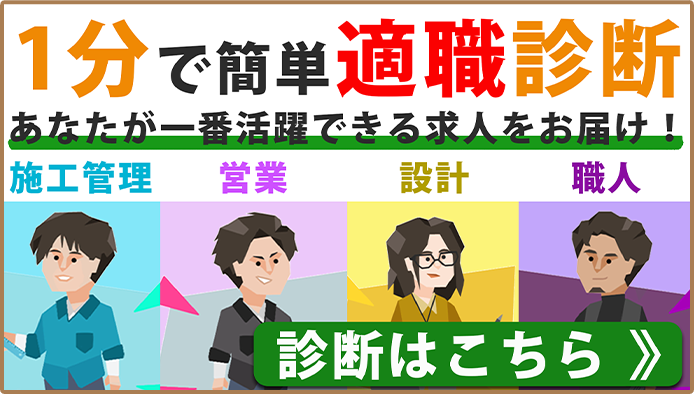
16タイプ診断の結果を基に施工管理タイプ、設計タイプ、営業タイプ、職人タイプに診断し、無料であなたが活躍できる求人をお届けします。
-
④フリーランス診断 NEW!!
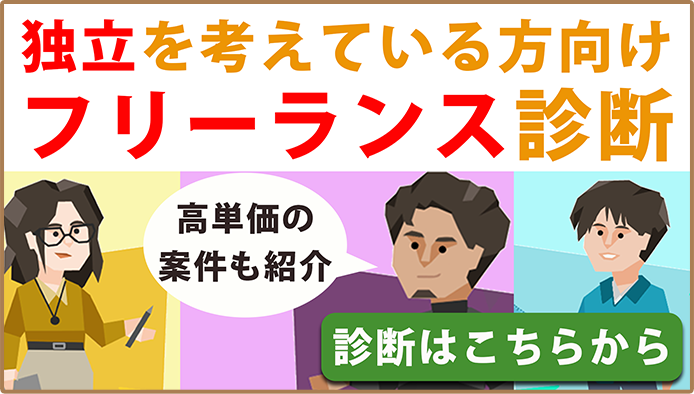
16タイプ診断の結果を基に職種に加え正社員とフリーランスのどちらの働き方が向いているかを診断します。フリーランスとして独立を考えている方へおすすめです。
-
⑤施工管理キャリア診断 NEW!!
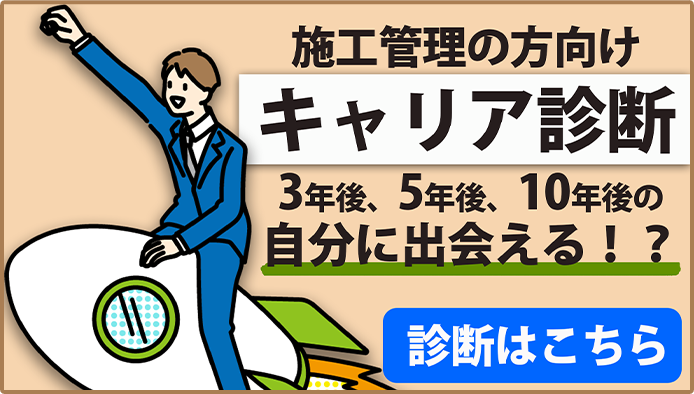
3年後、5年後、10年後の年収や休日、残業時間、役職などのシミュレーションができ、あなたのキャリアアップにつながる求人をお届けします。