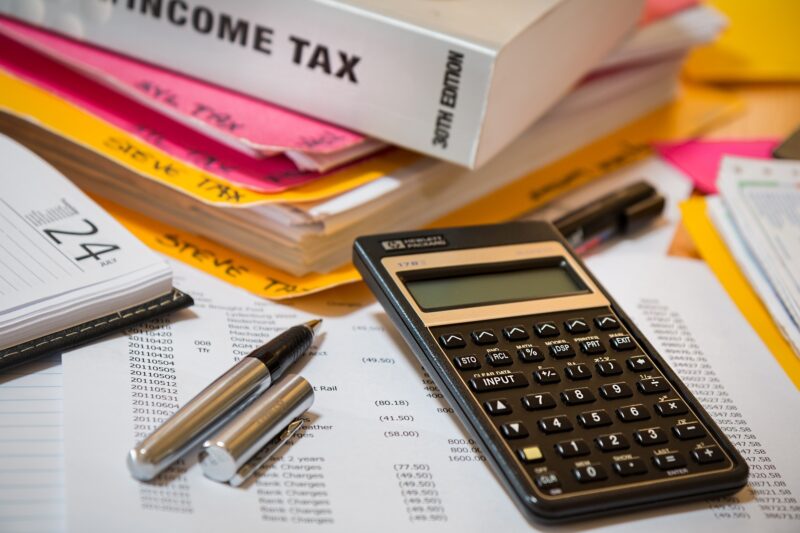建設業で外国人労働者を雇用する際の賃金や税金のルールと注意点を解説
建設業界では人手不足を背景に、外国人労働者の雇用が増加しています。
2025年現在、多くの企業が外国人材を活用していますが、その雇用には適切な賃金設定や税金の取り扱いなど、注意すべき点が多くあります。
なぜなら、外国人労働者の雇用には、最低賃金の遵守や在留資格に応じた税金の扱いなど、日本人労働者とは異なるルールが適用されるからです。
そこで本記事では、建設業で外国人労働者を雇用する際の賃金や税金に関する基本的なルールを解説するとともに、企業が押さえておくべき重要なポイントについて詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人労働者に適用される税金の基本的な仕組み
居住者と非居住者の区分
外国人労働者は、日本国内に住所があるか、または1年以上継続して居住している場合に「居住者」とみなされます。
一方、これに該当しない場合は「非居住者」とされます。
居住者は国内外の所得が課税対象となり、非居住者は国内所得のみが課税対象です。
滞在期間による課税対象の違い
滞在期間が1年以上の場合、居住者として国内外の所得が課税されます。一方、短期滞在者は非居住者として扱われ、国内で発生する所得のみが課税対象となります。
ただし、租税条約により免除される場合もありますので、専門家に確認するのがおすすめです。
源泉徴収の義務
雇用主は、外国人労働者の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。居住者の場合、年末調整が行われますが、非居住者は通常20.42%の税率で源泉徴収されます。
建設業における外国人労働者の税金の種類
所得税|居住区分による課税の違い
外国人労働者の所得税は、居住区分によって異なります。
居住者は国内外の所得が課税対象となり、累進課税が適用されます。
一方、非居住者は国内所得のみが課税対象で、20.42%の一律税率が適用されるのが一般的です。ただし、短期滞在者は租税条約によって免税となる場合があるため、十分注意しましょう。
住民税|支払い義務と計算方法
住民税は、前年の所得に基づき計算され、居住者が対象です。1月1日時点で日本に住所がある場合、特別徴収として給与から控除されます。
一方、非居住者は住民税の対象外です。
社会保険料|健康保険、年金、雇用保険の取り扱い
外国人労働者も日本人と同様に社会保険に加入する義務があります。健康保険、厚生年金保険、雇用保険が含まれ、保険料は労働者と雇用主が分担します。
派遣労働者の場合、条件により加入対象外となることもあります。
外国人労働者の所得税に関する特徴と手続き
居住者、非永住者、非居住者の区分
外国人労働者は「居住者」「非永住者」「非居住者」に区分されます。
居住者は国内外の所得が課税対象で、非永住者は国内所得と国外から送金された所得が対象です。非居住者は国内所得のみが課税対象となります。
短期納税者免税制度の適用条件
短期納税者免税制度は、滞在期間が183日以内、雇用主が非居住者、給与が日本国内で費用処理されていない場合に適用されます。
この制度により、所得税が免除される可能性があります。
年末調整時に必要な書類
年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「基礎控除申告書」などが必要です。
これらの書類を提出することで、控除が適用され、正確な税額が計算されます。
建設業で外国人を雇用する際の住民税の知識
住民税の課税対象と期間
住民税は、1月1日時点で日本に住所がある外国人労働者が対象となります。
前年の1月1日から12月31日までの所得に基づき課税され、6月から翌年5月までの12か月間にわたり支払います。
なお、非居住者は住民税の対象外です。
特別徴収義務者としての企業の役割
企業は、給与から住民税を天引きし、市区町村に納付する特別徴収義務を負います。これにより、従業員が住民税を滞納するリスクを軽減します。
なお、退職時に未納分を一括徴収する場合がありますので、専門家に確認するのがおすすめです。
納税管理人制度の活用
外国人労働者が帰国する際、住民税の支払いが完了していない場合は、納税管理人を選任する必要があります。
納税管理人は、労働者に代わり税金の手続きを行う役割を担い、市区町村に届け出を行います。
租税条約と課税免除の申請手続き
租税条約の概要と締結国
租税条約は、二重課税を防ぎ、国際的な経済活動を促進するために締結される協定です。
日本はアメリカ、イギリス、中国、インドなど多くの国と租税条約を結んでいます。
これにより、所得税や法人税の軽減や免除が可能となり、国際的な税務負担が調整されます。
課税免除申請の流れ
課税免除を受けるには、租税条約に基づく「租税条約に関する届出書」を作成し、所得の支払者を通じて税務署に提出しなければなりません。
なお、提出期限は、所得の支払を受ける日の前日までです。適用後、軽減税率が適用されます。
必要書類と提出先
必要書類には、「租税条約に関する届出書」や「居住者証明書」が含まれます。これらの書類は、所得の支払者を経由して、支払者(企業)の所轄税務署に提出します。
書類の不備がある場合、国内法の税率が適用されるため注意が必要です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
外国人労働者の賃金設定と注意点
最低賃金の遵守
外国人労働者にも最低賃金法が適用されます。地域ごとに定められた最低賃金を下回る賃金設定は違法であり、技能実習生や特定技能労働者も例外ではありません。
最低賃金を守らない場合、企業には罰則が科される可能性があるため、適正な雇用環境を整えることが重要です。
同一労働同一賃金の原則
外国人労働者にも「同一労働同一賃金」の原則が適用されます。そのため、同じ業務内容であれば、日本人と同等の賃金を支払わなければなりません。
不合理な賃金格差を防ぐためにも、業務内容やスキルに基づいた適正な賃金設定が重要です。
在留資格に応じた賃金基準
在留資格ごとに求められるスキルや業務内容が異なるため、賃金基準も変わります。
例えば、特定技能労働者には即戦力としての能力が求められるため、比較的高い賃金が設定されることが一般的です。
なお、適正な賃金設定は在留資格の取得にも影響する重要な要素です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
税金未納・滞納のリスクと対策
在留資格への影響
外国人労働者が税金を滞納すると、在留資格の更新や変更が認められない場合があります。
特に所得税や住民税の未納は、法務省の審査でマイナス要因となり、最悪の場合、在留資格の取り消しにつながる可能性があります。
企業の責任と対応策
企業は外国人労働者が税金を適切に納付できるよう支援する責任があります。
税務に関するオリエンテーションや相談窓口の設置、専門家との連携を通じて、労働者が税金の仕組みを理解し、滞納を防ぐ体制を整えることが重要です。
適切な税務管理の重要性
適切な税務管理は、労働者の安心と企業の信用を守るために不可欠です。
源泉徴収や住民税の特別徴収を確実に行い、滞納が発生した場合には速やかに対応することで、リスクを最小限に抑えることが重要です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
建設業における適切な外国人労働者の税務管理方法
正確な記録管理の方法
外国人労働者の税務管理には、給与、源泉徴収、社会保険料などの正確な記録が不可欠です。これにより、税務申告や監査に対応しやすくなります。
専用の管理ソフトやデジタルツールを活用し、記録の一元化と更新を徹底することで、ミスを防ぎ、効率的な管理が可能です。
税務専門家との連携
税務専門家との連携は、複雑な税務手続きや法改正への対応に役立ちます。
外国人労働者の税務に精通した専門家を活用することで、適切なアドバイスを受け、リスクを軽減できます。また、専門家の助言を基に、税務管理体制を強化することが重要です。
従業員教育と情報提供
外国人労働者に税務に関する基本的な知識を提供することは、滞納防止に効果的です。
税金の仕組みや納付方法を説明する研修を実施し、多言語対応の資料を配布することで、労働者が自身の税務義務を理解しやすくなります。
このような取り組みは、税務管理の円滑化に寄与する重要な要素です。
もし、外国人労働者の受け入れに関する疑問やお悩みのある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適な人材やソリューションを提供いたします。