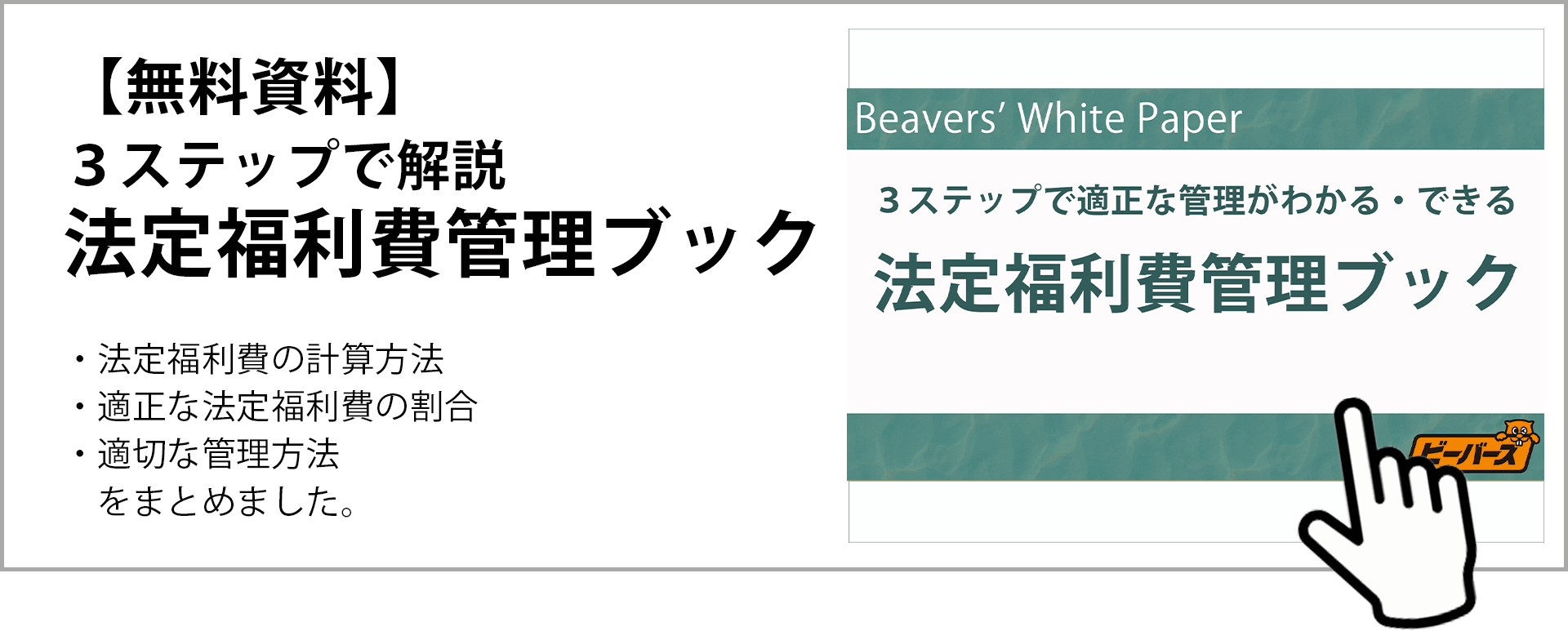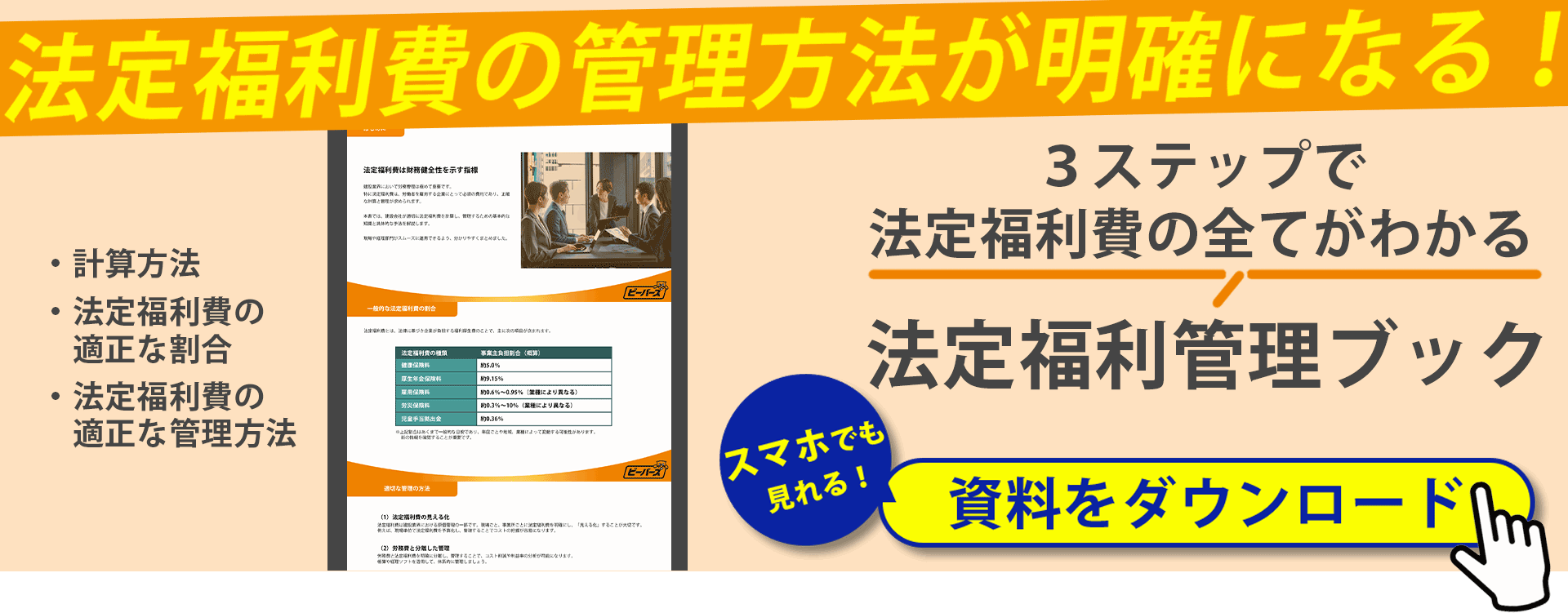建設業の法定福利費は何パーセントが目安?企業が注意すべきポイントも解説
建設 建設業界動向・情報Warning: Undefined array key 2 in /home/xb923971/beavers.co.jp/public_html/wp-content/plugins/rich-table-of-content/functions.php on line 332
Warning: Undefined array key 2 in /home/xb923971/beavers.co.jp/public_html/wp-content/plugins/rich-table-of-content/functions.php on line 332
建設業における法定福利費は、労務費に対して何パーセントが目安かを理解することが重要です。
企業が法定福利費の算出や適切な計上を怠ると、コンプライアンス違反や経営リスクを招くおそれがあります。
そのため、近年の保険料率の変動や法改正に配慮しながら、正確な算出方法と注意点を押さえることが大切です。
そこで今回は、建設業の法定福利費の適正割合について、企業が注意すべきポイントと共に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
▼法定福利費について、より詳しく解説した無料資料「法定福利費管理ブック」を以下から無料でダウンロードいただけます。
CHECK!
本記事では「法定福利費の適正割合と適性管理方法」をご紹介しておりますが、あくまで一般的な経営課題解決策の一部でしかありません。企業の抱える経営課題は様々であり、1社1社、見極めていく必要があります。
ビーバーズではあらゆる経営課題を解決するため、人材紹介、ヘッドハンティングサービスにとどまらず、採用コンサルティングやDX化支援など多様なサービスを実現しています。お困りの方はビーバーズにご相談いただけると幸いです。課題解決に向けて一緒に考えます。ビーバーズを利用するか否かは、その後にご判断いただければと思います。本記事でご紹介しているノウハウ以外にも様々な情報を提供できますので、まずはお気軽に下記のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
建設業における法定福利費の基礎知識

法定福利費とは?
法定福利費とは、企業が法律に基づいて従業員に提供しなければならない社会保障費用のことです。
具体的には健康保険や厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金などが含まれます。
建設業界では、これらの費用を労務費に見合った形で適正に計上することが求められ、違反すると法的リスクが生じます。
労務費に対する法定保険料率の仕組み
法定福利費は、労務費に対して一定の保険料率を乗じて算出します。この保険料率は健康保険や厚生年金、雇用保険など複数の保険料率を合算した数値です。
各保険料率は地域や業種によって異なり、建設業特有の労災保険率も加味されます。
企業はこれらの率を適切に反映させることで、正確な法定福利費を積算します。
保険料率の種類と構成要素
法定福利費に含まれる保険料率は、主に健康保険料率、厚生年金保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金によって構成されます。
これらは企業と従業員で負担割合が決められているものが多く、特に建設業界では労災保険料率が高めに設定されている点が特徴です。
建設業で特に高い理由
建設業界は労災事故や怪我のリスクが高いため、労災保険の保険料率が他業種に比べて高額に設定されています。
加えて、作業環境の安全確保や労働者の健康管理に重点が置かれていることも影響し、法定福利費全体の割合が比較的高くなる傾向があります。
法定福利費の法的背景
法定福利費は健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法など複数の法律に基づいて企業に負担が義務付けられています。
これにより、従業員の生活保障や労働安全が法的に守られており、違反した場合は罰則や行政指導の対象となります。
建設業特有の安全衛生確保の観点からも重要視されているのです。
建設業界の法定福利費は何パーセント?算出方法と目安を解説

建設業の一般的な法定福利費率
2025年時点の建設業における法定福利費率の目安は、労務費の15〜16%前後とされています。
これは健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険(40歳以上対象)などの事業主負担分の合計率で、地域や作業内容により若干の差があります。
例えば、健康保険は約5%、厚生年金は約9.15%、雇用保険は約1%、労災保険は0.25〜1.5%の範囲で設定されています。
保険料率の地域差や工種別違い
法定福利費の保険料率は、地域の社会保険組合や都道府県によって異なります。
また、労災保険料率は工種ごとの危険度に応じて変動し、建設業の中でも高所作業や危険度の高い工種は料率が高めに設定されているため注意が必要です。
これらの違いを考慮し、正確な料率設定と適用が求められます。
実務的な計算例と見積書の書き方
法定福利費は「労務費×法定福利費率」で計算します。例えば、労務費1000万円で料率16%の場合、法定福利費は160万円です。
見積書には法定福利費を明確に分けて記載し、内訳を示すことで透明性を確保します。
国土交通省のガイドラインに基づき、詳細な保険料率も併記して記載することが推奨されます。
改正に伴う最新動向
社会保険料率や労災保険料率は毎年見直されており、2025年も一部料率の微調整がありました。少子高齢化や労働環境の変化に対応するために保険制度も変化しています。
最新の料率情報を随時確認し、見積もりや経費計算に反映させることが、法令遵守や経営リスク回避のために不可欠です。
労災保険率の特性
労災保険料率は他の社会保険料率よりも変動幅が大きく、業種・工種ごとにリスク評価が異なります。
建設業は特に高リスクであるため、通常の業種より高めに設定されており、作業内容の危険性や事故発生率に応じて料率が上下します。
これにより、企業は労働安全に努めるインセンティブを持ちつつ保険料を支払っているのです。
参考資料:国土交通省「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」より
法定福利費の最新動向と2025年度の変更点

令和6年改正のポイントと企業への影響
2025年度(令和7年度)の法定福利費に関しては、社会保険料率や雇用保険料率の見直しが行われています。主なポイントは以下の通りです。
雇用保険料率の引き下げ
2022年度・2023年度と引き上げが続いていましたが、2025年度は0.1ポイント(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げられます。これにより、企業の負担がわずかに軽減されます。
健康保険料率・介護保険料率の改定
健康保険料率は都道府県ごとに見直しが行われ、引き上げ・引き下げが混在します。介護保険料率は全国一律で「1.59%」に引き下げられる予定です(2024年度は1.60%)。
厚生年金保険料率は据え置き
2017年9月以降「18.3%」で固定されており、2025年度も変更はありません。
労災保険料率は据え置き
2024年度に改定された料率が2026年度まで適用されるため、2025年度も変更はありません。
これらの改定により、建設業の法定福利費はおおむね約16%前後となりますが、都道府県や従業員構成によって変動します。企業は毎年の料率改定を正確に把握し、見積や経費計算に反映させることが重要です。
公共工事設計労務単価の改定と法定福利費
2025年度の公共工事設計労務単価も見直しが行われ、全国全職種単純平均で前年度比5.9%引き上げられました。この単価には、必要な法定福利費相当額が加算されるなど、技能者の処遇改善や社会保険加入の徹底が反映されています。
また、建設業法改正により、労務費や法定福利費の明確化・見積書記載の義務化が一層強化されています。これにより、元請・下請間での適正な費用負担や、労働者の社会保障確保が推進されています。
企業は、最新の設計労務単価や法定福利費率を常に確認し、公共工事の入札や見積作成時に正確に反映することが求められます。これを怠ると、受注機会の損失や行政指導のリスクが高まるため、注意が必要です。
企業が把握すべき法定福利費の具体的な計算方法

企業が把握すべき法定福利費の計算方法は、以下のステップに従って行います。
1.人件費の算出
まず、労務にかかる総額を算出します。これには、直接的な賃金だけでなく、残業代、休日手当、賞与なども含まれます。
2.法定保険料率の確認
次に、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料などの各種社会保険の保険料率を確認します。これらの率は、都道府県や業種、事業規模によって異なる場合があるため、最新の情報を基にする必要があります。
3.法定福利費の計算
人件費総額に対して、確認した法定保険料率を乗じて、法定福利費を計算します。計算式は以下の通りです。
- 法定福利費=人件費総額×法定保険料率
4.見積書への明示
計算された法定福利費は、見積書に明示する必要があります。これにより、適正な価格での受注が可能となり、労働者の社会保障を確保することができます。
以上の計算方法と手順により、企業は法定福利費を正確に把握し、適切に管理することが重要です。
法定福利費について解説した無料資料「法定福利費管理ブック」を無料でダウンロードする
建設業での法定福利費の適切な管理の方法

建設業での法定福利費の適切な管理方法には、以下のステップが含まれます。
1.法定福利費の内訳を明示する
法定福利費を内訳明示した見積書を作成し、下請企業が元請企業に提出する見積書に法定福利費を明示します。これにより、社会保険等の加入に必要な金額を確保し、公平で健全な競争環境の構築と就労環境の改善を図ります。
2.法定福利費の範囲を理解する
法定福利費には、健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)、雇用保険料の事業主負担分が含まれます。労災保険料は事業主が全額負担します。
3.保険料率の適用
保険料率は、協会けんぽや日本年金機構、厚生労働省のウェブサイトなどから入手可能です。適用する保険料率は、事業の種類や地域によって異なるため、最新の情報を基に計算します。
4.法定福利費の計算
労務費総額に各保険の保険料率を乗じて法定福利費を計算します。また、工事費や工事数量に基づく平均的な法定福利費の割合を用いて簡便に算出する方法もあります。
5.見積書への記載
計算された法定福利費は、見積書に事業主負担分として明示します。これにより、元請企業と協議を行い、最終的な金額を決定します。
6.適用除外者の取り扱い
常時使用する労働者が5人未満の個人事業所や一人親方などは、健康保険、厚生年金保険に加入する義務がないため、法定福利費から除外します。
7.見積書の提出と確認
見積書を提出する際には、法定福利費を内訳明示することが重要です。元請企業は、見積書に法定福利費が記載されているかを確認し、下請企業は必ず法定福利費を見積書に記載する必要があります。
これらのステップに従って、建設業における法定福利費の適切な管理を行うことが可能です。正確な保険料率の把握と適切な見積もりは、健全な運営と労働者の社会保障を確保するために不可欠です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
【法定福利費の適正な管理にお困りの方向け】
法定福利費の計算方法、適用範囲、そして最適な割合についての理解は、企業が直面する法的リスクを回避し、従業員との良好な関係を築くためにも重要です。
しかし、法定福利費の適正な管理にはリソースが奪われ、なかなか手が回らないという方も多いはず。
そこでおすすめするのがビーバーズのお役立ち資料「法定福利費管理ブック」です。
3ステップで計算方法、適正な割合、適切な管理方法を提示しています。
大変人気な資料のため、現在無料で提供しています。
法定福利費の管理に手が回らない、適正な割合がわからない、という方は、今すぐダウンロードしましょう!
法定福利費の割合に影響を与える要因

法定福利費の割合に影響を与える要因としては、以下のようなものが挙げられます。
従業員の数
従業員が多ければ多いほど、支払う法定福利費の総額が増加します。
労働生産性
機械化、合理化、IT化、DXの推進により労働生産性を高めることで、法定福利費の負担を相対的に軽減することが可能です。
ビーバーズではDXコンサルティングサービスを提供しており、法定福利費をはじめとするさまざまな費用を一元管理できるデジタルツールの選定・導入を支援しております。人材にかかる費用だけでなく、仕入れコストや支払い、給与管理に至るまでの経理業務を効果的に効率化できます。もし、デジタルツールの導入や、優秀なデジタル人材の採用にお悩みの方は、ぜひビーバーズにご相談ください。貴社の経営課題の解決策を一緒にお考えいたします。
給与水準
法定福利費は従業員の給与と連動しており、給与が高いほど法定福利費も増加します。
これらの要素を考慮に入れて、企業は適切な法定福利費の割合を計算し、従業員にとって良好な労働環境を提供するための計画を立てることが大切です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
企業が注意すべき法定福利費のポイント

計上漏れや過小申告のリスク
建設業における法定福利費の計上漏れや過小申告は、法令違反に該当し、追徴課税や行政指導の対象となるリスクがあります。
特に下請企業が元請から法定福利費相当額を受け取っていない場合、労働者の社会保険未加入や適切な保険料納付が困難になり、企業の信用低下や経営リスク拡大につながります。正確な計上が不可欠です。
下請代金に含めるべき費用範囲
下請代金に含まれるべき法定福利費は、労務費にかかる事業主負担の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険など)及び子ども・子育て拠出金が基本です。
これにより、労働者の福利厚生が保証され、公正な取引を実現します。計上範囲が不明瞭だと契約トラブルや法的問題が生じるため注意が必要です。
監査や調査での確認ポイント
監査・調査においては、見積書に法定福利費項目が明示されているか、労務費に対する法定福利費の計算根拠が適切かが重点的に確認されます。
また、保険料の納付履歴や従業員の社会保険加入証明も審査対象です。不備や虚偽申告があれば改善指導や行政処分の可能性があります。
保険料率の定期的な見直し
社会保険料率や労災保険料率は年度ごとに見直されることが一般的で、最新の料率適用を怠ると過不足問題が生じます。
また、地域や業種別の差異もあるため、定期的に確認し適切な料率を適用する必要があります。特に建設業特有の労災保険料率は変動が大きいため注意が求められます。
労務費との整合性確保
法定福利費の算出は労務費をベースとしているため、労務費との整合性を確保することが重要です。
労務費の過少計上があると法定福利費も不正確になります。そこで、給与支払い記録や労働時間管理と連携し、適正な労務費計算とそれに対応する正確な福利費算出を実現することが、適切な見積もり作成や申告に不可欠です。
法定福利費のコスト管理と効率化の方法

労務費と福利費のバランス調整
建設業においては、労務費と法定福利費のバランスを適切に調整することが重要です。
労務費を抑えすぎると労働者のモチベーションや作業効率が低下し、逆に法定福利費が過大になるとコスト増につながります。
適切な人件費配分を行い、福利厚生の充実とコスト競争力の両立を目指すことが経営安定のポイントです。
業務効率化による間接コスト削減
法定福利費の管理を効率化するためには、紙ベースの手作業からクラウドや業務管理ツールの導入が効果的です。
手入力によるミスや重複作業を減らし、計算や書類作成の自動化を促進します。
これにより労働時間の短縮や人的ミスの防止が進み、管理部門の間接コストが大幅に削減されます。
賃金構造の見直しによる節税効果
給与体系や賃金構造を見直し、基本給と各種手当のバランスを工夫することで、法定福利費の負担軽減を図ることが可能です。
例えば、法定福利費の算出基盤となる賃金総額を適正に調整しつつ、必要な手当を区分管理することで、社会保険料の節税効果や経費の最適化が期待できます。
社会保険料の適正管理方法
社会保険料は加入者の賃金に基づいて算出されるため、正確な賃金台帳の管理が不可欠です。
給与データと社会保険料率を最新の状態に保つほか、不整合や未加入を防ぐための定期的なチェック体制が求められます。
適正管理により不要な追徴やペナルティを回避できます。
福利費計算ツールの活用
近年は法定福利費の計算を自動化するソフトやクラウドツールが普及し、複雑な保険料率や従業員情報の変更も迅速に反映可能です。ツール利用により計算精度が向上し、作業負担が大幅に軽減されます。また、見積書作成や帳票出力も容易になり、コスト管理の透明性も高まります。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
建設業における法定福利費の最新動向

建設業における法定福利費の最新動向については、以下のような情報があります。
令和6年3月からの適用分
公共工事設計労務単価が改訂され、全国全職種単純平均で前年度比5.9%引き上げられることになりました。これは、平成25年度の改訂から12年連続の引き上げであり、全国全職種加重平均値が23,600円となっています。
労務単価の構成
労務単価には、事業主が負担すべき必要経費(法定福利費、安全管理費等)は含まれていません。事業主が下請代金に必要経費分を計上しない、または下請代金から必要経費を値引くことは不当行為とされています。
法定福利費の算出
法定福利費は、労務費総額に法定保険料率を乗じて計算されます。具体的な算出方法としては、工事費に含まれる平均的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらかじめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便に算出することも考えられます。
これらの動向は、建設業における労働者の福利厚生の改善と、公平で健全な競争環境の構築に向けた取り組みの一環として重要です。企業はこれらの情報を基に、適切な法定福利費の計算と、労働者に対する適正な給与の支払いを行うことが重要です。
法定福利費の適切な管理とコスト最適化

DX・デジタルツール活用による管理効率化
建設業界では、法定福利費の計算や管理をデジタルツールで自動化することで、業務効率とコスト最適化を実現しています。給与計算システムを使用すれば、最新の法定福利費率を反映し、給与明細作成や社会保険料の自動計算が可能です。これにより、手作業による計算ミスやチェック漏れを防ぎ、経理担当者の負担を大幅に軽減できます。さらに、月次・四半期ごとのコスト分析やデータの一元管理も容易になり、経営判断の精度向上にも貢献します。
外部コンサル・社労士の活用メリット
法定福利費の管理や最適化には、外部の専門家(社会保険労務士やコンサルタント)の活用も有効です。専門家は最新の法改正や料率変更への対応、適切な経費計上方法の指導、助成金・補助金の活用アドバイスなど、実務に直結したサポートを提供します。特に複雑なケースや人員構成が多様な企業では、専門家のチェックによりリスクを最小化し、法令違反や過少計上を未然に防ぐことができます。
不正・見落としを防ぐチェックポイント
法定福利費の適切な管理には、不正や見落としを防ぐための定期的なチェックが欠かせません。主なポイントは以下の通りです。
- 毎年の料率改定や法改正情報を必ず確認し、システムや管理表に反映させる
- 給与計算や保険料計算の自動化ツールを導入し、手作業によるミスを防ぐ
- 月次・四半期ごとにコスト分析を実施し、異常値や未払いがないかを定期点検する
- 外部専門家による定期監査やアドバイスを受ける
これらの対策を組み合わせることで、法定福利費の適正管理とコスト最適化を同時に実現し、企業経営の健全化に寄与します。
法定福利費の未払い・過少計上リスクと法的責任

未払いが発覚した場合の企業リスク
法定福利費(社会保険料や労働保険料)の未払いが発覚すると、企業は重大な法的・経営的リスクを負います。まず、社会保険の未加入や未払いは法律違反となり、行政指導や是正命令の対象となります。特に建設業界では、公共工事の受注資格停止や元請企業との取引停止につながるケースもあるため、十分注意しましょう。
また、未払い分については遡及して納付を命じられ、加算金や延滞金が課されることもあります。損益計算書上では利益が過大計上されるため、粉飾決算とみなされるリスクもあり、金融機関や取引先からの信用失墜、最悪の場合は倒産リスクにも発展します。
行政指導・監査の最新事例
近年、国土交通省や労働基準監督署による建設業界への監査・指導が強化されています。
公共工事では、法定福利費の適切な計上・支払いが義務化されており、未加入・未払い企業への発注は発注者側も法令違反とみなされるケースが増えています。実際に、未払いが発覚した企業には是正命令や指導が行われ、改善が見られない場合は指名停止や入札資格の剥奪など厳しい措置が取られているため注意が必要です。監査では、会計処理の誤りや未払計上漏れ、給与計算と社会保険料のズレなども重点的にチェックされており、会計処理の正確性と適切な管理体制の構築が不可欠です。
このように、法定福利費の未払い・過少計上は企業経営に深刻な影響を及ぼすため、毎月の計上・納付状況を正確に管理し、法改正や料率変更にも迅速に対応することが重要です。
法定福利費のよくある誤解について

1.法定福利費と福利厚生費の混同
法定福利費は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険・子ども子育て拠出金など、法律で企業に負担が義務付けられた社会保険料を指します。一方、福利厚生費は、社員旅行や健康診断、慶弔見舞金など企業が任意で支出する費用であり、法定福利費とは明確に区別されます。
2.法定福利費は全額会社負担だと思われがち
実際には、社会保険料の多くは企業と従業員が折半で負担します。会社が負担する分のみが法定福利費として経費計上され、従業員負担分は預り金として処理されます。
3.法定福利費の消費税扱いの誤解
法定福利費も他の工事費用と同様に消費税の課税対象となります。
4.法定福利費の計算方法の誤解
労務費総額に法定保険料率を乗じて算出するのが基本です。健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、適用料率を必ず確認する必要があります。
下請・協力会社とのトラブル事例

1.見積書への法定福利費未記載によるトラブル
元請企業から下請企業に対し、法定福利費の内訳を明示した見積書の提出が求められる場面が増えています。未記載の場合、受注機会を逃したり、契約後に追加請求のトラブルが発生することがあります。
2.法定福利費の過少計上・未払い問題
下請企業が法定福利費を適切に計上・納付していないと、元請企業が行政指導や監査の対象となる場合があります。公共工事では特に厳格にチェックされ、未払いが発覚すると指名停止や契約解除につながることもあります。
3.保険料率の認識違いによる請求トラブル
健康保険料率や介護保険料率は地域や従業員構成で異なるため、元請・下請間で認識がずれていると、請求額の不一致や精算トラブルが発生しやすくなります。
4.協力会社の社会保険未加入問題
下請・協力会社が社会保険に未加入の場合、元請企業が発注を見送るケースや、行政からの指導対象となる事例が増えています。社会保険加入の徹底が業界全体の信頼性向上に不可欠です。
このような誤解やトラブルを防ぐためには、法定福利費の基本的な仕組みや最新のルールを正しく理解し、見積書や契約書で明確に内訳を記載することが重要です。
弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング
- 若手高度外国人材紹介
- 事業承継型M&A仲介
- DXコンサルティング
- 採用コンサルティング
- 助成金コンサルティング
どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。
法定福利費について解説した無料資料「法定福利費管理ブック」を無料でダウンロードする
建設業における法定福利費のまとめ
このように、建設業を営む企業にとっては、法定福利費は見落としてはならない費用の一つです。しかし、法定福利費を適切に管理することで、忙しい自社のリソースを奪われる可能性があるため、なかなか手が回らないという方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、法定福利費をはじめとするさまざまな費用を一元管理できるデジタルツールの活用です。デジタルツールを導入することで、人材にかかる費用だけでなく、仕入れコストや支払い、給与管理に至るまでの経理業務を効果的に効率化できます。
そこでもし、デジタルツールの導入や、優秀なデジタル人材の採用にお悩みがある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。